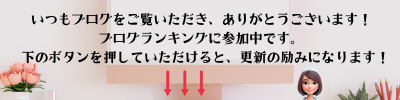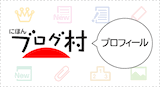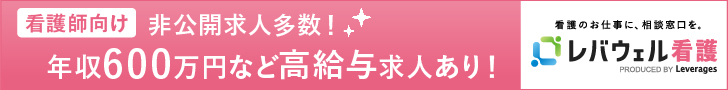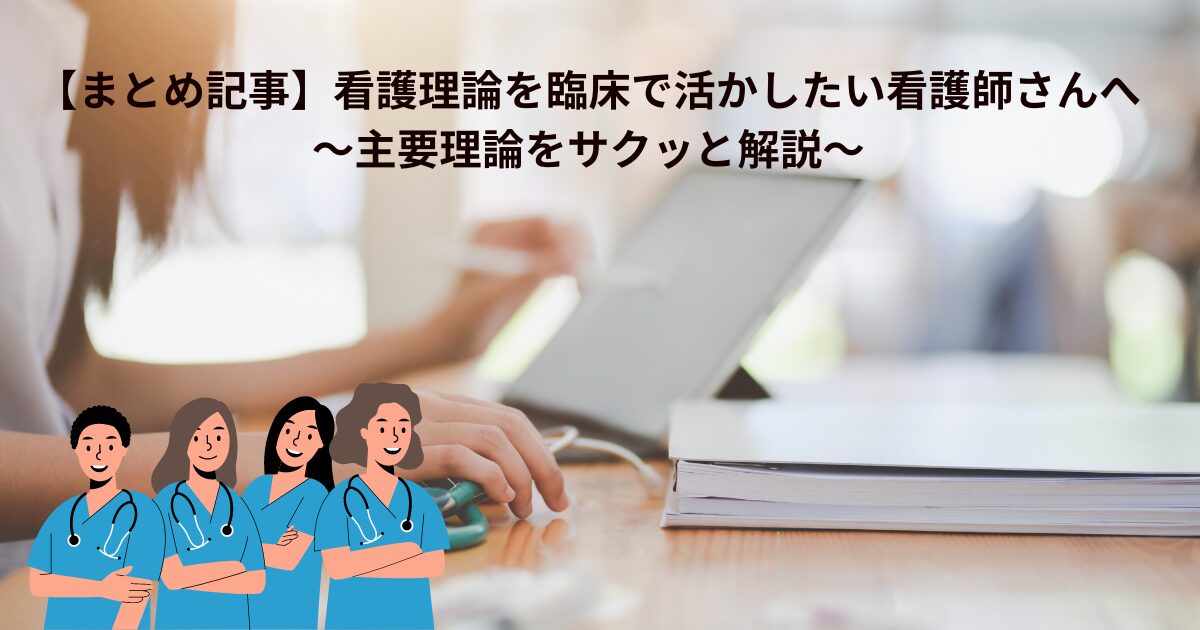こんにちは。このブログの管理者
ゆるーりすと のぴまゆです。
このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。
それではゆるーりとご覧ください。
こんな方におすすめ
- 終末期・緩和ケアに携わる看護師
- 看護学生・実習中の学生
- 在宅看護や訪問看護に関心のある方
- 尊厳を支えるケアを学びたい医療職
目次
■はじめに
先日、日経メディカルで掲載された記事
「最期までトイレに行きたい山田さん」(廣橋 猛 先生)を読み、
まさに私自身が日々の看護の中で感じていることと重なり、胸が熱くなりました。
終末期に近づいた患者さんが、「トイレに行きたい」と何度も訴える場面。
安全のためにおむつをすすめても、尿道カテーテルを提案しても、
「トイレで排泄したい」と譲らない方がいらっしゃいます。
「おむつの方が楽なのに」「転倒したら危ないのに」──
そんな思いが頭をよぎる一方で、
“その方にとってトイレに行くという行為の意味”を
看護師としてどう受け止めるか、深く考えさせられます。

■「自分でトイレに行く」ことの意味
記事の中の山田さんは、骨転移の痛みに苦しみながらも、
「自分の足でトイレに行きたい」と願い続けていました。
看護師たちは、2人がかりで介助し、痛みを最小限に抑えるために
レスキュー薬の注射を工夫しながら、その希望を支え続けたそうです。
安全や効率を考えれば、おむつやカテーテルが合理的かもしれません。
しかし、山田さんにとって「トイレに行く」というのは、
“自分のことを自分でできる”という人間としての尊厳そのものでした。
私自身も、かつて受け持った患者さんを思い出します。
亡くなる2時間前まで、「トイレに行きたい」と意思表示され、
私たち看護師3人で介助しました。
その方はトイレから戻られると、静かに微笑まれ、
まるで「やり遂げた」と言わんばかりの安堵の表情を浮かべていました。
今でも忘れられない瞬間です。

■ヘンダーソンの基本的欲求と「排泄の自立」
看護理論家バージニア・ヘンダーソンは、
人間の基本的欲求として「排泄すること」を挙げています。
そして、看護の目的は「患者が自立して生活できるよう援助すること」だと述べています。
終末期であっても、「自分で排泄したい」という思いは、
単なる生理的な欲求ではなく、“人間として自立して生きたい”という意思の表れ。
ヘンダーソンの言葉を借りれば、
看護師が果たすべき役割は、患者の自立を奪うのではなく、
可能な限りその自立を支援することにあります。
-

-
バージニア・ヘンダーソンとその看護哲学~「看護の基本となるもの」と「看護論」のエッセンス~
こんにちは。このブログの管理者 ゆるーりすと のぴまゆです。 このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。 それではゆるーりとご覧ください。 こんな方におすすめ ヘ ...
続きを見る

■諦めさせるのではなく、「本人のペースで決める」
現場では、転倒リスク、介助負担、限られた人員などの現実があります。
それでも、看護師の都合で「もうトイレはやめましょう」と
一方的に決めてはいけないのだと思います。
患者さん自身が「今日はもう無理かもしれない」と感じたとき、
その決断を尊重できるよう、見守る看護が大切です。
廣橋先生の記事の中で、山田さんは
「もうトイレは難しいかもしれない」と自ら口にしたとき、
看護師が「これまでよくがんばりましたね」と声をかけたそうです。
その瞬間、山田さんは「最後まで自分でできて良かったよ」と
穏やかに答えられたといいます。
その言葉には、「生き切った」という誇りが滲んでいました。
看護師にとっても、それは何よりの報いだったのではないでしょうか。

■尊厳を守るということ
“排泄を自分でしたい”という願いは、
最後まで「人として生きたい」という力の表れです。
それをどう支えるかは、看護師の姿勢にかかっています。
看護とは、「治すこと」だけではなく、
“生きる力を支えること”。
そして“その人らしさ”を守り抜くことです。
終末期の「トイレに行きたい」という小さな願いは、
実はその人が「まだ自分で生きたい」と願う
生命のメッセージなのかもしれません。

■まとめ~最期までその人らしく
最期までトイレに行きたいという願い。
そこに込められた思いをどう支えるか──。
それは、看護師にとって「人間の尊厳を守る看護」とは何かを問うテーマです。
患者さんが「もうトイレは難しい」と言うその日まで、
私たちは見守り、寄り添い、支える存在でありたい。
そしてその姿勢こそが、
ヘンダーソンの理論が目指した“自立を支援する看護”の本質なのだと思います。

ヴァージニア・ヘンダーソン著 『看護の基本となるもの』 日本看護協会出版会

今日もゆるーりとね💕