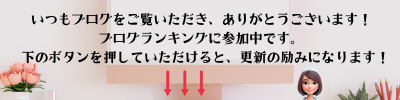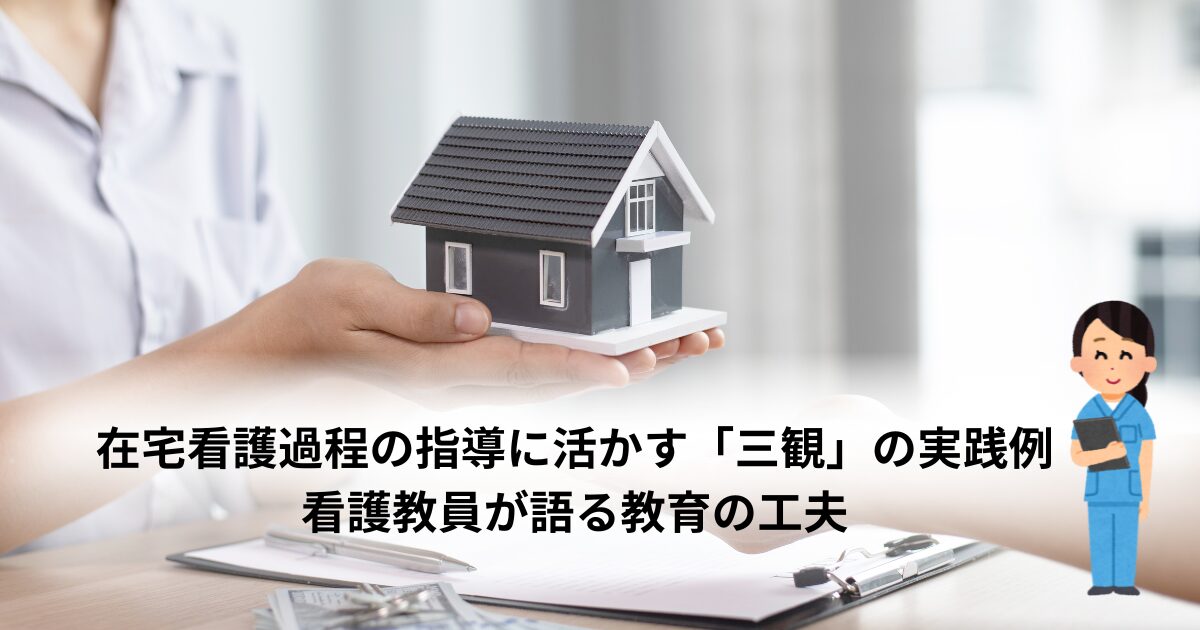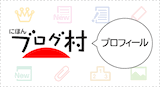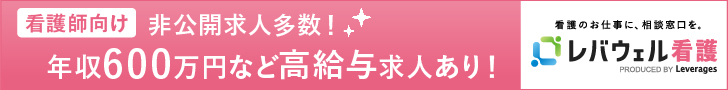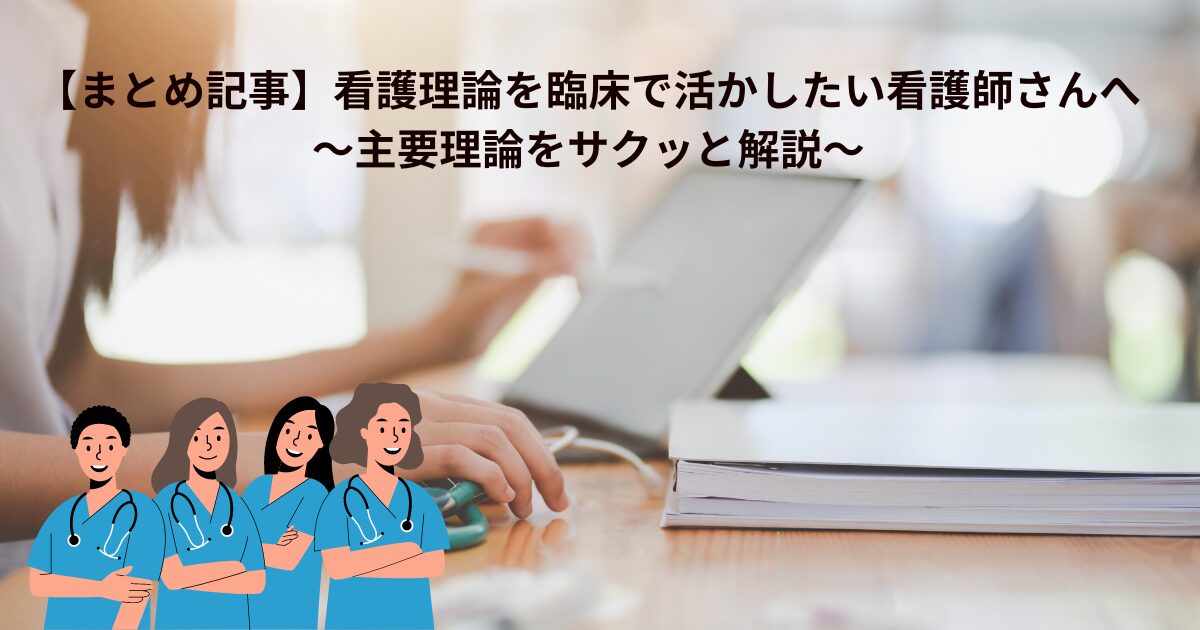こんにちは。このブログの管理者
ゆるーりすと のぴまゆです。
このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。
それではゆるーりとご覧ください。
こんな方におすすめ
- 看護学校で教鞭をとる現役教員
- 教育実習中の看護師・大学院生
- 看護教育に関心のある看護師・指導者
- 授業設計のヒントを探している方
目次
【はじめに】
看護教育の現場では、授業設計にあたり「教材観・学生観・指導観」という“教育の三観”が重要な視点となります。
-

-
看護教員・実習指導者に求められる“教育の三観”とは?学生観・指導観・教材観が授業と指導を変える
こんにちは。このブログの管理者 ゆるーりすと のぴまゆです。 このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。 それではゆるーりとご覧ください。 こんな方におすすめ 授 ...
続きを見る
今回は、私が実際に「在宅看護過程Ⅰ」の単元で三観を明確にしたうえで指導にあたった事例をご紹介します。
これは以前、看護教員養成講習会で作成した自身のレポートをもとに構成したものです。
三観を意識することで、学生の学びを深める授業づくりができることを実感しています。

【1. 教材観:単元設定の背景とねらい】
■ 単元名:「在宅看護過程Ⅰ」
■ 単元設定の理由と教材観
この単元では、学生が既習の看護過程の知識を活かし、在宅における看護計画立案ができる力を育てることをねらいとしています。
在宅看護では、病院と異なり“生活の場”であるという特徴があります。
療養者と家族の暮らしに寄り添いながら、限られた支援の中で“その人らしい生き方”を支える看護が求められます。
教材観のポイント
・看護過程の基本は病院も在宅も共通だが、視点の違いを学ばせる
・医療と生活が密接に関わる在宅の現場において、療養者と家族の関係性、介護力などを踏まえた支援が必要
・幅広く個別性の高いニーズに対応できるよう、QOLの視点を重視したアセスメント力を育てる

【2. 学生観:学生のレディネスと教育的配慮】
学生は2年次の7か月目であり、これまでに看護過程の展開は複数の授業や実習で学んでいます。
ただし、それは主に病院内での看護を想定した内容でした。
一方、在宅看護においては「生活の場」での支援が求められ、これまでの学びとは異なる視点が必要になります。
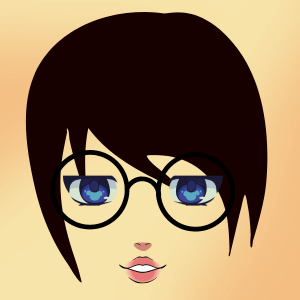
これまでの学習を結びつかせながら、指導設計をします。

学生観のポイント
・核家族化で異世代との関わりが乏しく、対人関係スキルが未発達な学生も多い
・情報収集の視点が狭く、必要な情報に気づきにくい傾向がある
・既習内容(施設での看護過程)と在宅看護過程との違いに気付かせる支援が必要
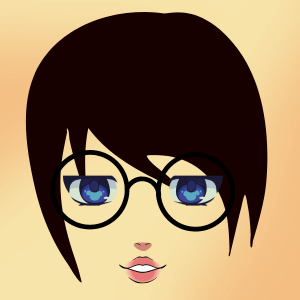
ここでもノールズのアンドラゴジー理論やデューイの経験型アプローチなどが有効です。
-

-
経験から学ぶ看護教育とは?~デューイとノールズの理論に学ぶ実習指導と評価のあり方~
こんにちは。このブログの管理者 ゆるーりすと のぴまゆです。 このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。 それではゆるーりとご覧ください。 こんな方におすすめ 看 ...
続きを見る

【3. 指導観:三観に基づいた指導方法の工夫】
指導の柱は、「既習内容を想起させながら、在宅ならではの視点に気付かせる」ことです。
そのために、以下のような具体的な方法を用いて授業を構成しました。
指導法の実際
1.DVD教材の活用とグループワーク
→ 在宅看護の実際を視覚で捉え、気づきを深める
2.視覚教材で情報収集の理解を促進
→ 「在宅看護における情報」とは何かをグループワークで掘り下げる
3.事例を用いた情報収集の時期と方法の指導
→ 時系列を意識し、計画的な支援ができる力を養う
4.QOLを意識した看護計画の立案演習
→ 家族を含めた生活の質に焦点を当てた支援を検討させる

【まとめ:三観が導く教育の質】
三観を明確にすることで、単なる知識伝達ではなく、学生のレディネスに応じた効果的な指導が可能になります。
とくに在宅看護のように“生活”と“医療”が交差する分野では、教材の特性、学生の特性、そしてそれに応じた指導方法の三つがしっかりと結びついていることが、学生の成長に直結します。

【おわりに:看護教員・指導者に向けて】
この記事は、現場で奮闘されている看護教員やこれから教育に携わる方へのヒントとなれば幸いです。
三観に基づいた授業づくりは、学生に「気づき」をもたらし、臨床で活きる思考力を育てる大きな力になります。
今後も、教育の質を高める工夫を一緒に考えていきましょう。

今日もゆるーりとね💕