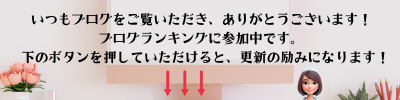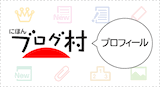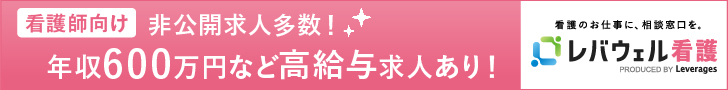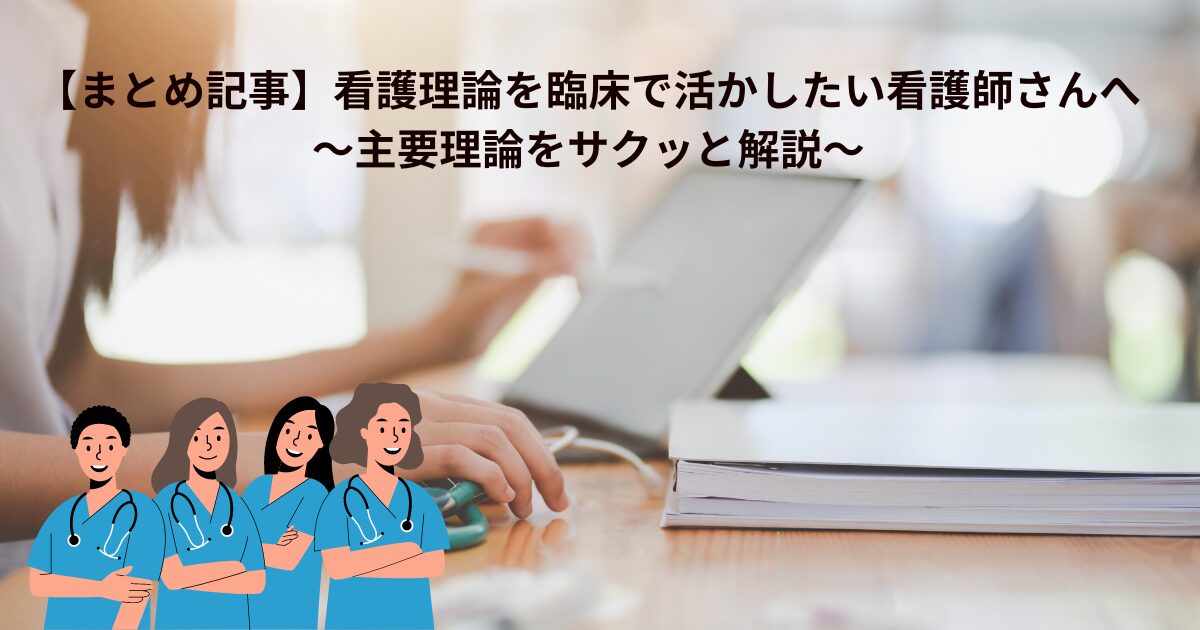こんにちは。このブログの管理者
ゆるーりすと のぴまゆです。
このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。
それではゆるーりとご覧ください。
こんな方におすすめ
- 子どもの発達に不安を感じている親御さん
- 保育士・幼稚園教諭・学校の先生
- 看護師・医療職
- 子育て支援に関わる支援者(児童発達支援、放デイスタッフなど)
- 情報収集中の妊娠・育児中のママパパ
目次
◆発達障害(神経発達症)を理解するために知っておきたいこと
(看護師ブロガーの視点と、母としての実体験も交えて)
最近、「発達が気になるのですが…」「落ち着きがないので相談したい」といった声を耳にする機会が、とても増えたと思いませんか?
実際、小児科外来では毎日のように発達に関する相談が寄せられており、もはや発達障害は“特別な疾患”ではなく、どの現場でも出会う身近な問題になっています。
文部科学省の調査では、知的遅れがないにも関わらず行動面で大きな困難を示す小中学生は全体の約5%。
つまり 20人に1人、クラスに1〜2人は神経発達症の特性を持つ子どもがいる 計算になります。
そんな背景もあり、小児科だけでなく、保育・教育、そして地域医療や看護の現場でもこのテーマに触れる機会が増えてきました。
今日は、日経メディカルの記事「もう“専門外”と言わせない!発達障害を診るコツ」を参考に、神経発達症について分かりやすくまとめながら、4人の子を育てた母としての私の経験も交えて、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

◆「発達障害」から「神経発達症」へ
2013年、DSM-5の改訂により「発達障害」は Neurodevelopmental Disorders(神経発達症) という包括概念に整理されました。
日本語で「症」としたのは、
「障害」という言葉が子どもへのスティグマにつながらないように…という社会的な配慮からです。
もちろん「発達障害」という言葉もまだ一般的ではありますが、今後はよりやさしい表現として 「神経発達症」 が広がっていくと思います。
神経発達症には…
・自閉スペクトラム症(ASD)
・注意欠如多動症(ADHD)
・限局性学習症(LD)
・知的発達症
・コミュニケーション症
・チック症などの運動症群
と、非常に幅広い状態が含まれています。

◆神経発達症は「脳の特性」
特性があることで、
・空気が読みづらい
・落ち着いて座っていられない
・会話がかみ合いにくい
・感覚の過敏さや鈍さがある
など、日常生活に“困りごと”として現れてきます。
大切なのは、これは 努力不足ではなく「脳の特性」 であるという視点。
本人が一番困っていることも少なくありません。

◆一般小児科医が身につけるべき3つのポイント
専門医だけでは地域の相談をカバーしきれない今、一般小児科でも以下の3つの力が必須です。
・発達相談の基本的な診療
・紹介が必要なケースの見極め
・専門受診までの一般的な支援
実はこれ、医師だけではなく、看護師や保育士、教育者、そして親御さんにも役立つ視点です。
◆問診のコツ:事前準備と“安心できる場作り”がすべて
発達相談では、いきなり詳しく聞き出す必要はありません。
むしろ事前問診票を使い、家族も準備してくる方が安心。
診察室では、
「今日は痛いことはしません」
「何に困っているか一緒に考えましょう」
と説明し、子どもが安全だと感じられる場作りが何より大切です。
親御さんへの問診では、
「どうして今日ここに来たのか」
「何を一番心配しているのか」
を丁寧に聞くことで、支援の方向性が見えてきます。

◆専門家に紹介すべきケース
以下のような場合は早めの専門相談が必要です。
・発達の退行がある
・てんかん・身体的異常を疑う場合
・不登校や集団行動が極めて困難
・暴力・自傷・強い不安など精神症状が重い
・保護者の不安が非常に強い場合
ただし、
「紹介する=ギブアップ」ではありません。
「多職種チームで支える」ためのステップです。
◆専門受診までにできること(ここが一番大事)
・生活リズムを整える
・見通しのある生活にする(急な変更は苦手)
・指示は一つずつ、分かりやすく
・できたことを褒める習慣
・本人も困っている、という視点の共有
・児童発達支援センター・放デイの活用
・「まあいいか」と思える余裕を持つ
これだけでも家庭のストレスがグッと減ります。
実際「まあいいか」と思う気持ち、これは経験的に本当に大事だと思います。

◆母としての経験:長女の「ことばの教室」
実は私自身、4人の子育ての中で、それぞれの特性に悩んだ時期がありました。
特に長女は幼いころ言葉の発達がゆっくりで、
「ことばの教室(言語障害通級指導教室)」 に通わせた経験があります。
そこで専門の先生と一緒に、
・発音の練習
・言語理解のサポート
・コミュニケーションの練習
などを続けたことで、本人の自信にもつながりました。
親として悩むのは決して珍しいことではありません。
むしろほとんどの親御さんが、子どもの「特性」に向き合う瞬間があります。
だからこそ今回の記事は、
悩んでいる親御さんの背中をそっと押してくれる内容 だと思いました。
私自身、このテーマはとても身近で、そして大切な話題だと感じています。
そして、私の長女は今、立派に保育士として働いて、結婚して旦那さんと子どもと平和に暮らせています。

◆まとめ
・神経発達症は特別な疾患ではなく、誰もが出会う身近な“特性”
・話を丁寧にきく「入り口」が何より大切
・専門紹介の見極めと、一般的な支援で早期対応が可能
・診断よりも「理解」と「寄り添う姿勢」が治療の出発点
・親子で一つずつできることを重ねていけば大丈夫
子どもの発達に悩む親御さんは本当に多いです。
でも、正しい知識と少しのサポートがあれば、子どもたちは自分の力を存分に発揮できます。
発達に悩んでいる方や、その支援に携わる皆さんの力に少しでもなれますように。

今日もゆるーりとね💕