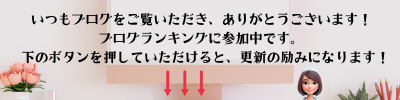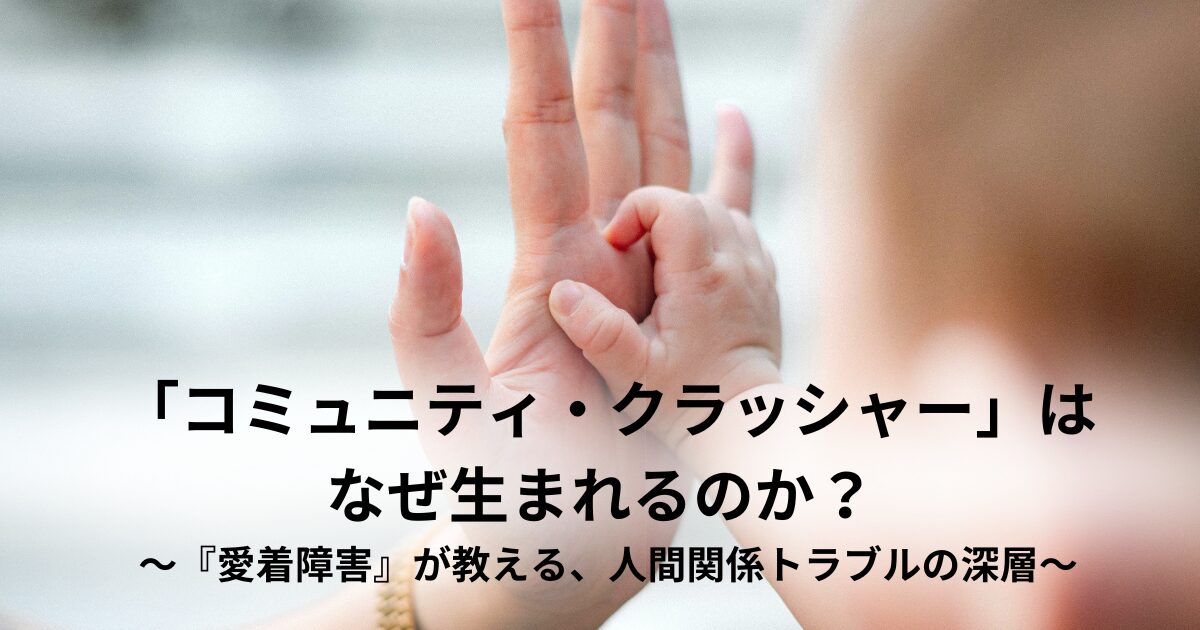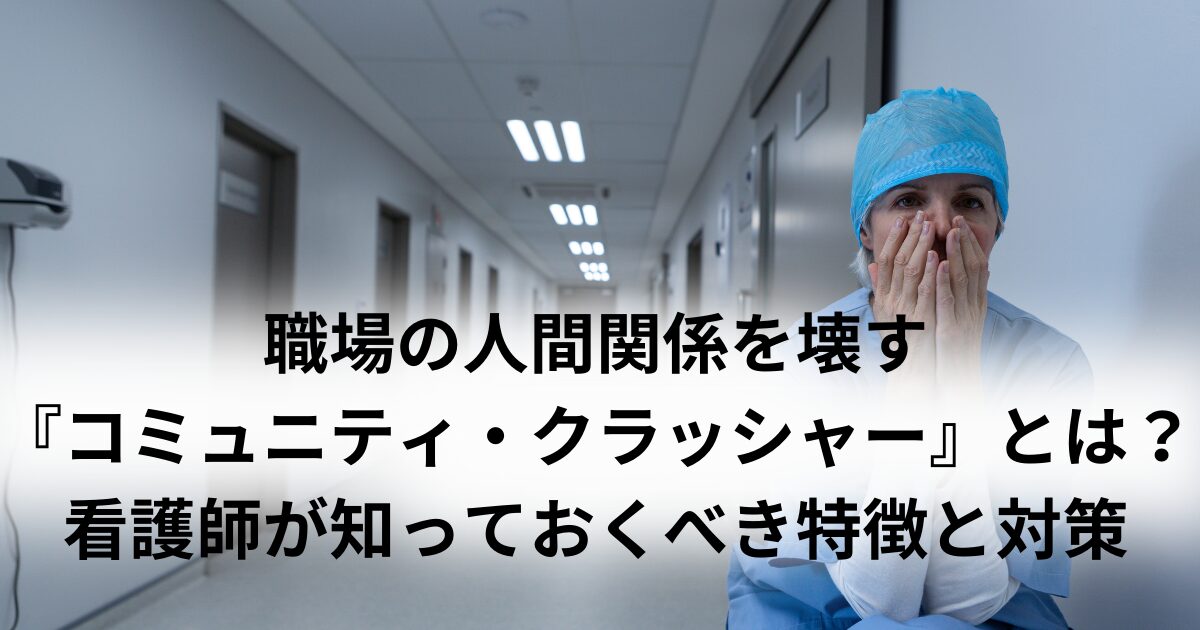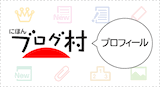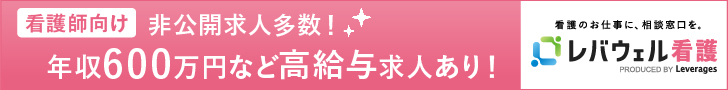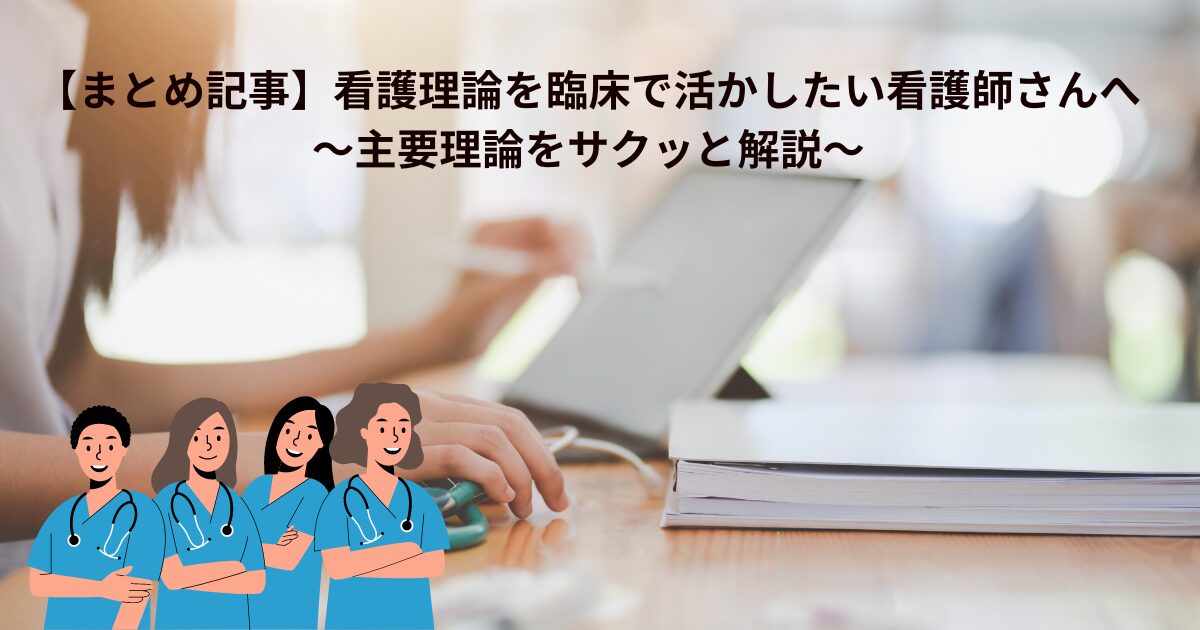こんにちは。このブログの管理者
ゆるーりすと のぴまゆです。
このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。
それではゆるーりとご覧ください。
こんな方におすすめ
- 職場で「扱いにくい人」に悩んでいる人
- 人間関係にモヤモヤを抱えている人
- 心理学や人の心の仕組みに興味のある人
- 管理職・リーダーとしてチームをまとめている人
目次
はじめに
職場やグループの雰囲気を乱す存在、「コミュニティ・クラッシャー」。
前回の記事では、その特徴や行動パターンについてお話しました。
-

-
職場の人間関係を壊す『コミュニティ・クラッシャー』とは?看護師が知っておくべき特徴と対策
こんにちは。このブログの管理者 ゆるーりすと のぴまゆです。 このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。 それではゆるーりとご覧ください。 こんな方におすすめ 病 ...
続きを見る
今回は、なぜそんな人が生まれてしまうのか——その「原因」について考えてみたいと思います。
看護の世界でも、チームの場を乱すような人がいると、雰囲気も悪くなり、業務にも影響が出ることもありますよね。
ヒントになったのは、精神科医・岡田尊司先生の著書『愛着障害』です。
1.コミュニティ・クラッシャーの行動の特徴
職場や地域コミュニティで、こんな行動をする人はいませんか?
・傷つきやすい、相手に悪気なくても「自分を否定された」と感じてしまう.
・意見が通らないと感情的になり、とんでもない行動をとる
・素直になれず、過度に意地を張る
・仲間内で分断を起こす、対立を煽る
実はこれらの行動には、共通する心理的背景があると言われています。

2.『愛着障害』がもたらす影響
岡田尊司氏によれば、「愛着障害」とは、幼少期に十分な愛情や安心を得られなかったことで形成される「心のクセ」のようなもの。
親との安定した関係が築けなかった子どもは、自分が愛される存在だと信じる力、つまり自己肯定感を持ちづらくなります。
その結果、大人になってからも、他人からの評価に過敏になり、傷つきやすく、感情の起伏が激しくなりがちです。
『愛着障害』の中で紹介されている特徴の中に、以下のような行動が挙げられています。
①アドバイスや注意を悪い方に受け取ってしまう場合も
例えば「ちょっとここ直してもらえる?」と言われただけで、「否定された」「嫌われている」と思ってしまうなど、ネガティブに反応しやすい傾向があります。
②小さなことでも大きく反応してしまう
感情の起伏が激しく、ちょっとした注意でも突然怒ったり泣いたり、「もうやらない!」と癇癪をおこすなど、とんでもないアクションになりがちです。
③実は甘えたいのに、素直にならずに意地を張ってしまう
自分の気持ちをうまく伝えられず、強がったり、周囲に対して反発してしまうことがあります。
これは、コミュニティ・クラッシャーの行動と重なります。
3.「壊す」ことで安心しようとする心理
私たちから見て「なぜそんなことを…?」と思ってしまうような行動も、本人にとっては「自分を守るための防衛反応」である場合があります。
「他人を攻撃することで、自分の存在価値を伝える」
「自分が信頼できないから、誰も信じられず、距離を取ったり、もしくは他人との距離の取り方がわからない」
「注目されないと不安になるので、周りを巻き込み職場をかき乱す」
彼女たちの行動の根底には、「安心できる人間関係を築く力が育たなかった」という悲しい背景があるのかもしれません。

4.現場でよくある場面
ところで、こんな看護師がいたとします。
・「私は昔からこんなやり方でやってきた!」と新人指導に強く口を出し、他のスタッフのやり方を否定する。
・チーム会議では不満ばかり言って場を重たくする。
このようなケースでは、問題のある行動の背景に、深い不安や孤独感が隠れていることもあります。

5.どう対応すればよいか
まず、問題行動をそのまま放置してはいけません。
チームや職場全体の雰囲気を守るためにも、適切な境界線を守ることは大切です。
しかし一方で、「なぜこの人はこんな行動をとるのか?」と一歩踏み込んでみることで、関係が少しは変わるのかも知れません。
・感情ではなく、冷静に事実を相手に伝える
怒りの感情を持ち込まず、「○○という場面で、△△が起きたよね」と、感情を駆り立てずに事実だけを伝えましょう。
・一対一で、落ち着いて話す時間をつくる
みんなの前で注意するのではなく、静かな場所でゆっくり話す時間をもつと、相手も防衛的に話に聞きやすくなります。
・否定するのではなく、「あなたにも大事な役割がある」と伝える
相手の良いところや貢献している部分を認める声かけが大切です。
・必要があれば、専門的なサポートへつなげる
本人が悩んでいる様子があれば、医療職やカウンセラーなど、専門的な支援につなぐことも一つの選択肢です。
大切なのは、共感と距離感のバランスです。

まとめ
コミュニティ・クラッシャーは、ただの「困った人」ではありません。
その背景には、満たされなかった愛情や、壊れてしまった信頼感があることが多いです。
岡田尊司先生の『愛着障害』は、そのような人の行動を冷静に考え、対応するための大きなヒントを与えてくれる一冊です。
看護の現場でも、人間関係に悩んでいる方は、一度読んでみる価値のある本だと感じました。
👇 岡田尊司 著 書籍

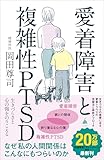
愛着障害と複雑性PTSD 生きづらさと心の傷をのりこえる (SB新書)

愛着障害の克服~「愛着アプローチ」で、人は変われる~ (光文社新書)

マンガでわかる 愛着障害 自分を知り、幸せになるためのレッスン

今日もゆるーりとね💕