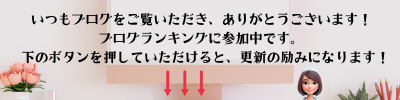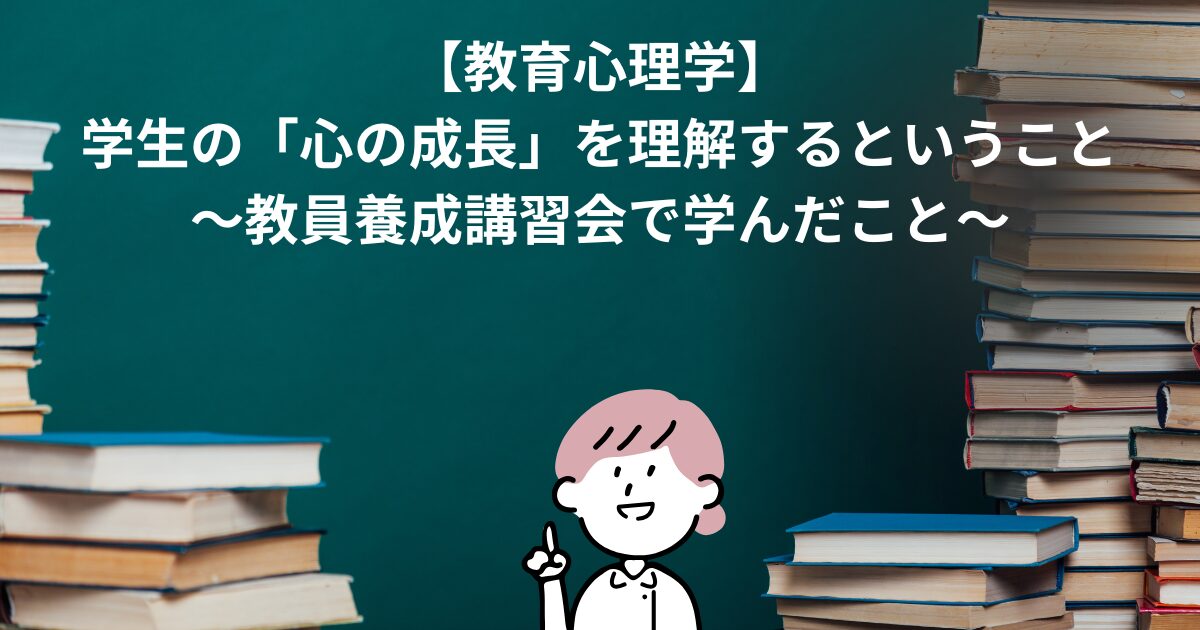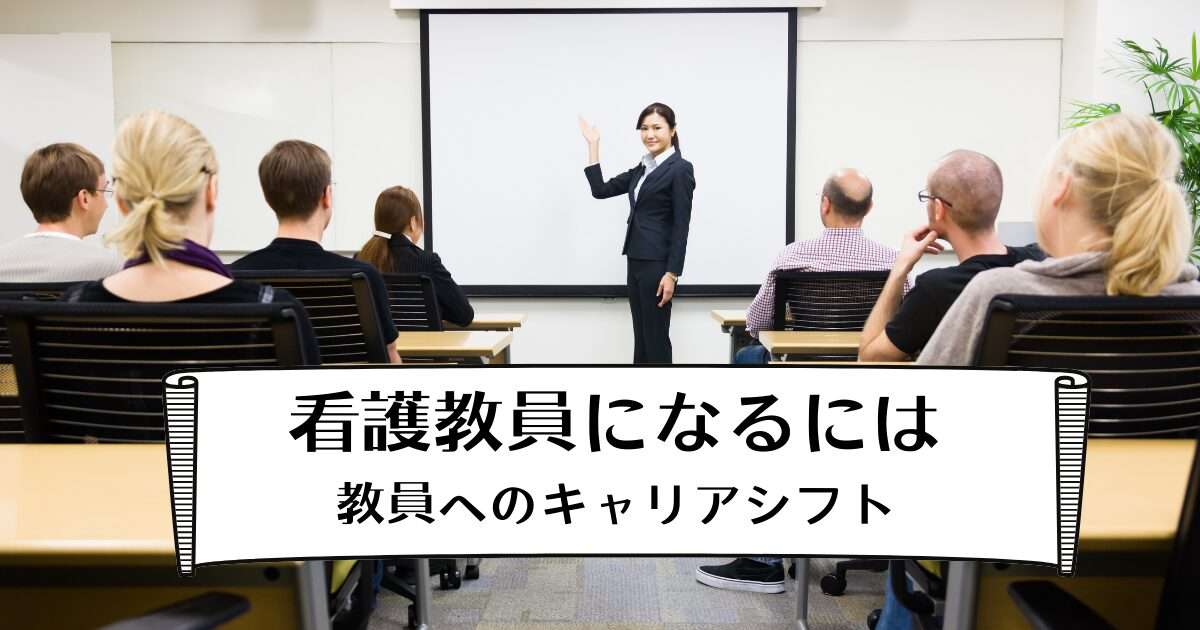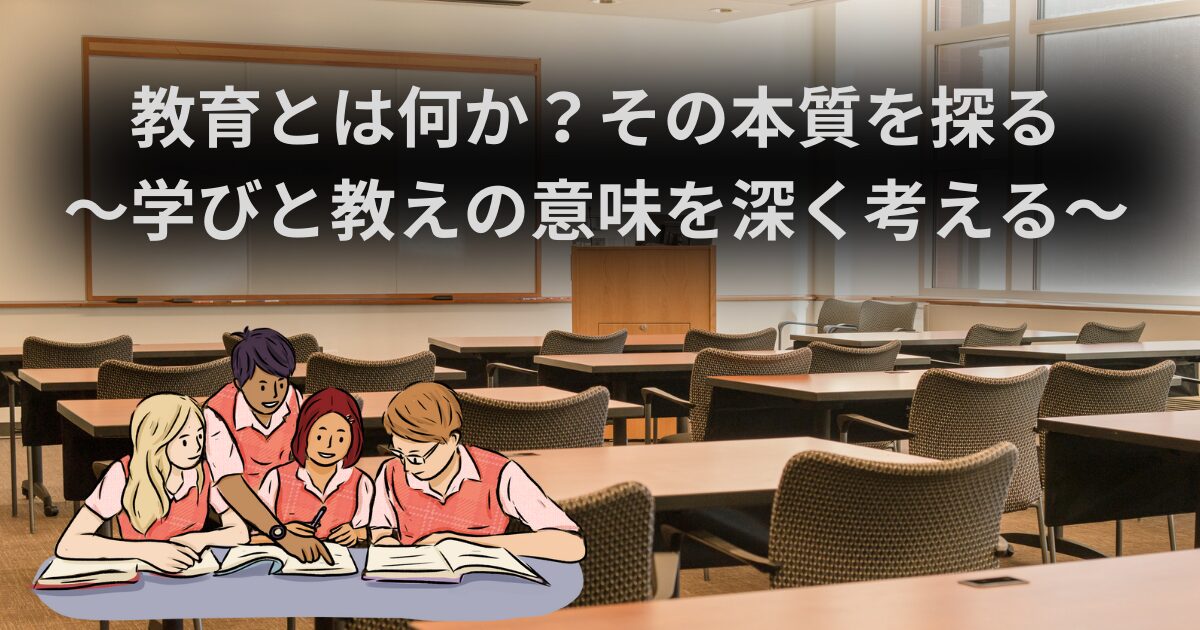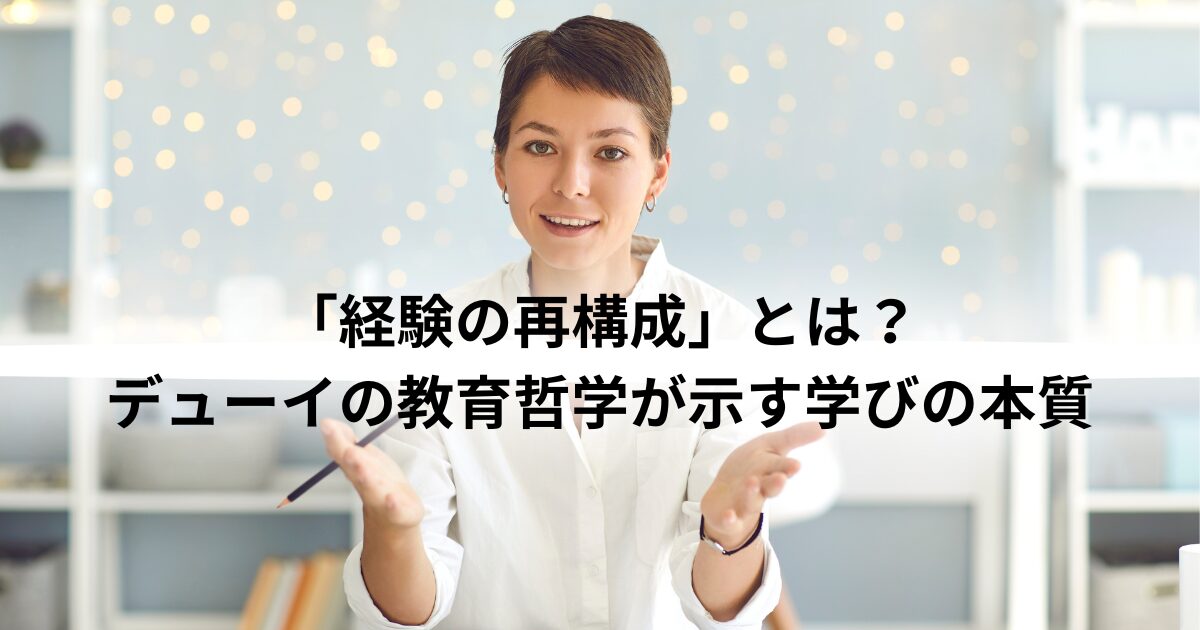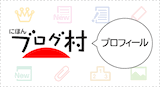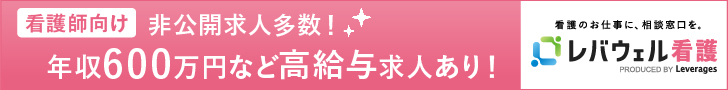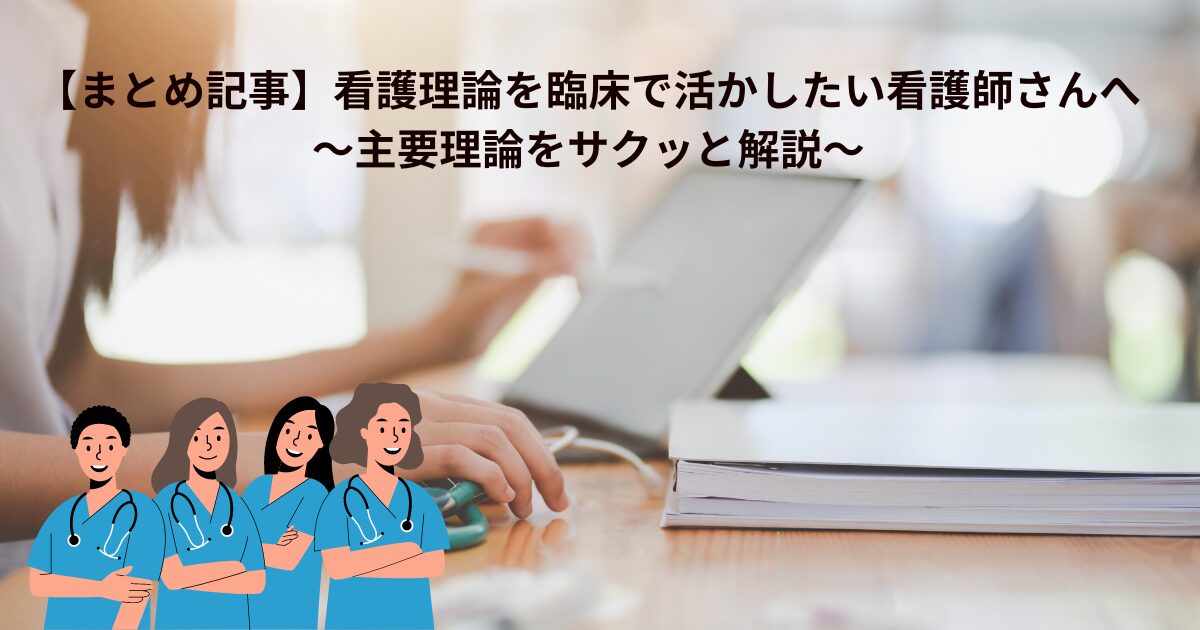こんにちは。このブログの管理者
ゆるーりすと のぴまゆです。
このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。
それではゆるーりとご覧ください。
こんな方におすすめ
- 看護教員・実習指導者として学生理解を深めたい方
- 看護教育に心理学的視点を取り入れたい方
- 教育現場で「学生のやる気」に悩んでいる方
目次
🌱はじめに
看護学生の指導に携わる中で、あらためて感じるのは「知識を教えること」と「心を育てること」は同義ではないということです。
今回は、教員養成講習会で受講した「教育心理学」(講師:福田みのり先生)での学びを、私なりの視点でまとめてみました。
-

-
看護教員になるには~教員へのキャリアシフト~
こんにちは。このブログの管理者 ゆるーりすと のぴまゆです。 このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。 それではゆるーりとご覧ください。 こんな方 ...
続きを見る
1.心理学とは「見えない心を見ようとする学問」
心理学という言葉から、多くの人は「人の心を読む」「深層心理」などを思い浮かべるでしょう。
確かに心理学は目に見えないものを扱いますが、それは決して神秘的な学問ではなく、人の感情・思考・行動を科学的に理解するための学問です。
授業では「学生が心を揺さぶられるのは、どんな時か?」という問いが印象的でした。
感情が揺さぶられたとき、人の温かさに触れたとき――その瞬間、私たちは“心”という存在を実感します。

2.教育とは「愛しみ(ヲシム)」の行為である
「教える」と「育てる」には、実は深い語源的な意味があります。
“教える”はもともと「愛惜(ヲシム)」に通じ、相手を大切に思う心から導く行為であるとされます。
一方で“育てる”は「巣立ち」に由来し、成長を見守りながら助けるという意味があります。
教育とは、知識の伝達ではなく、愛と見守りの営みなのだと感じました。

-

-
教育とは何か?その本質を探る:学びと教えの意味を深く考える
こんにちは。このブログの管理者 ゆるーりすと のぴまゆです。 このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。 それではゆるーりとご覧ください。 こんな方におすすめ 教 ...
続きを見る
3.教育心理学の目的~学びを支える4つの視点~
教育心理学は、教育者が学習者に「適切な働きかけ」をすることで、成長を支援する学問です。
授業では次の4つの課題が示されました。
発達の理解:発達段階に応じた指導がなければ教育は成立しない。
学習の理解:主体的に学ぶ意欲(動機づけ)をどう高めるか。
評価の理解:評価のないところに教育の進歩はない。
人格の理解:知育だけでなく、情意を育む教育が必要。
看護教育でも、学生の「できた・できない」だけでなく、感情の動きや成長のプロセスを見取ることが大切です。

4.発達心理学からみる「青年期」とアイデンティティの形成
青年期の学生たちは、「自分とは何か」を模索する時期にあります。
エリクソンは、発達段階を8つに分け、その中で「自我同一性(アイデンティティ)」の確立を最重要課題としました。
思春期の身体的変化や進路選択など、彼らは多くの不安を抱えながら成長しています。
教師や指導者に求められるのは、承認し、支える他者としての存在です。
この「心理的モラトリアム期」に寄り添えるかどうかが、学生の自己形成に大きな影響を与えます。

5.動機づけの理論と教育の工夫
学生のやる気は「内発的動機づけ」と「外発的動機づけ」のバランスで成り立っています。
内発的動機づけは「知りたい・成長したい」という内側から湧く意欲、外発的動機づけは「褒められたい・報酬を得たい」という外からの刺激です。
教育現場では、報酬がかえってやる気を下げる「アンダーマイニング現象」にも注意が必要です。
逆に「頑張りが評価された」という実感は、「エンハシング効果」を生み、やる気を高めます。
学生の自己効力感(自分の行動が結果を変えるという感覚)を育てる関わりこそ、教育心理学の実践といえるでしょう。
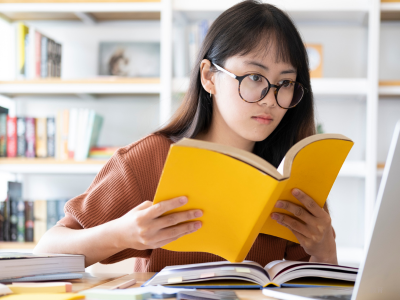
-

-
「経験の再構成」とは?デューイの教育哲学が示す学びの本質
こんにちは。このブログの管理者 ゆるーりすと のぴまゆです。 このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。 それではゆるーりとご覧ください。 こんな方におすすめ デ ...
続きを見る
6.学習と記憶のメカニズムを知る
心理学の面白さは、学びの「仕組み」が科学的に説明できること。
例えば、学習内容が長期記憶に残るためには、意味づけ・反復・文脈の一致が重要です。
神経心理学の研究では、「学んだ場所や状況と似た環境で思い出しやすい(文脈効果)」ことが実証されています。
また、「生成効果」と呼ばれる現象では、自分の頭で考えて作り出した情報の方が記憶に残ることが分かっています。
つまり、学生自身が“考え・発見する授業”をデザインすることが、真の学習支援につながるのです。

7.集団の中で育つ「個性」と「社会性」
授業では、学級集団の中での人間関係の育ちについても学びました。
集団には、探り合い → 同一化 → 規範形成 → 役割分化という発達過程があります。
看護学校のクラスでも、グループワークを通じて「社会的促進」が起こることがあります。
一方で、他者の存在が逆に抑制を生む「社会的怠惰」も生じる――
この両面を理解し、チームワークの中で個性を生かすことが教育者に求められます。
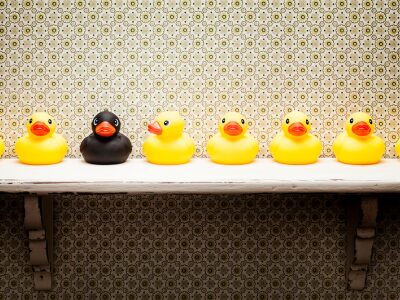
8.リーダーシップ理論と看護教育
教師のリーダーシップには、独裁型・民主型・放任型があります。
その中でも、目標達成(P)と人間関係の維持(M)を両立する「PM型リーダーシップ」が最も高い教育効果を示すとされます。
看護教育においても、学生を“指導する”だけでなく、“信頼して任せる”バランスが重要です。
学生が安心して挑戦できる環境づくりこそ、教育心理学の実践といえるでしょう。

9.学びの本質は「相互作用」である
教育は、教える側と学ぶ側の双方向の関わり(相互作用)です。
学生の特性を観察し、発達段階に合わせた働きかけをする――
その積み重ねが、学習意欲と成長を支えることを、私はこの講義で強く実感しました。
今後も、根拠に基づく教授方法を取り入れ、学生が主体的に学び、自らの成長を実感できる授業づくりを続けていきたいと思います。

🌱まとめ:教育心理学が教えてくれること
・教育は「愛しみ」と「見守り」の行為である。
・学習者の発達段階と心理的課題を理解することが教育の出発点。
・教師はリーダーであると同時に、援助者でもある。
・「考える授業」「感じる授業」「対話する授業」が学生を伸ばす。

今日もゆるーりとね💕