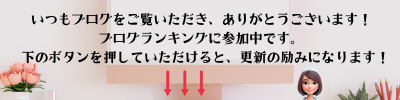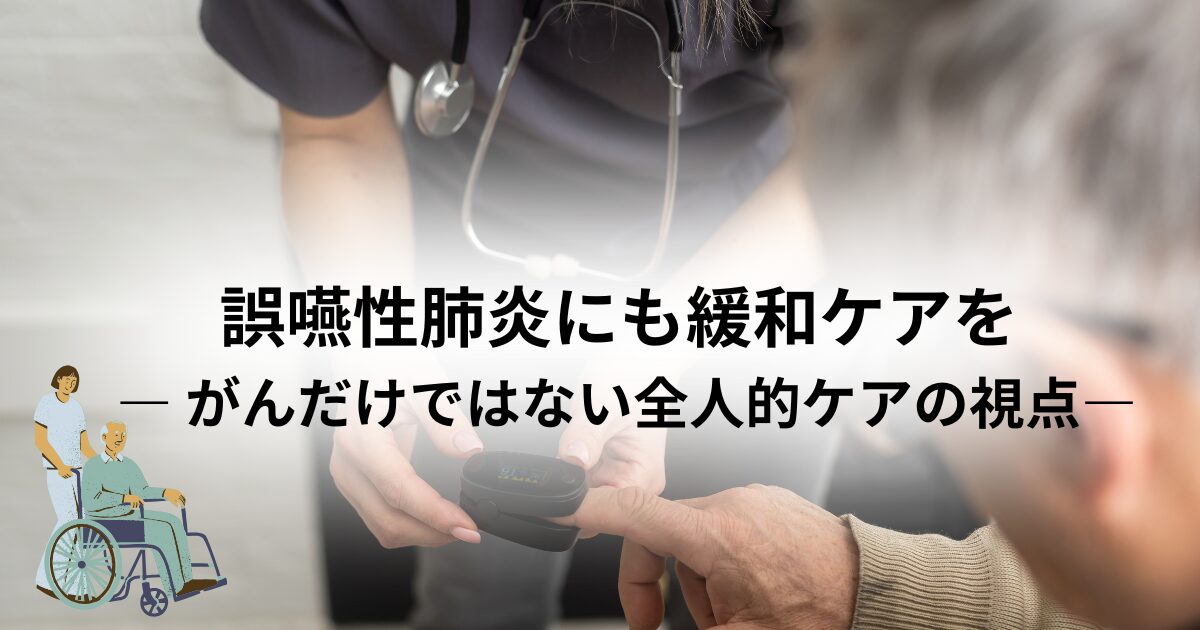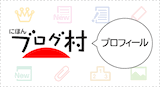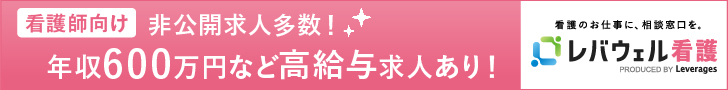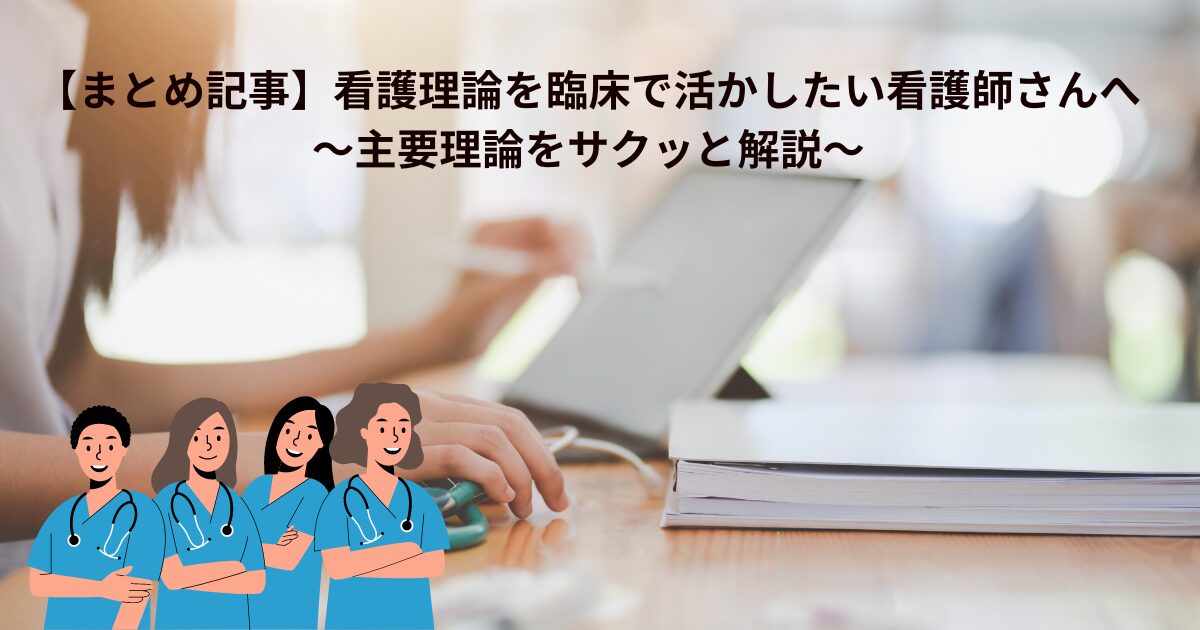こんにちは。このブログの管理者
ゆるーりすと のぴまゆです。
このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。
それではゆるーりとご覧ください。
こんな方におすすめ
- 高齢者看護や緩和ケアに関心のある看護師
- 誤嚥性肺炎患者を担当する医療者
- 在宅医療や介護に携わる方
- 家族として患者を支える立場の方
はじめに
誤嚥性肺炎は高齢者に多く、再発や入退院を繰り返す大きな課題です。
しかし「緩和ケア」と聞くと、多くの方はがんの終末期をイメージされるのではないでしょうか。
先日、福岡で開催された第30回日本緩和医療学会学術大会で、「誤嚥性肺炎にも緩和ケアを」という教育講演が行われました。
私は緩和ケア病棟で働く看護師として、その内容に大きな気づきを得ました。
また日経メディカルにも「誤嚥性肺炎の患者さんにも緩和ケアを」という記事を吉松 由貴先生が執筆されていたのを拝見しました。
今回はその学びと、自分自身の現場経験を交えながらお伝えします。

誤嚥性肺炎は緩和ケアの対象か?
日本では依然として「緩和ケア=がんの終末期」という認識が根強いです。確かに緩和ケア病棟も、その多くは「がん」を対象としています。
私の勤務する病棟でも「誤嚥性肺炎だけでは入院できない」という現状があります。
しかし、緩和ケアの本質は「全人的苦痛の緩和」にあります。
身体的、精神的、社会的、スピリチュアル――4つの苦痛にアプローチするのが緩和ケアです。
これはがんに限らず、誤嚥性肺炎の患者さんにも当てはまります。

誤嚥性肺炎に特有の苦痛
誤嚥性肺炎は、他の疾患にはない独特の苦しみを伴います。
・身体的苦痛:呼吸困難、咳や痰、胸膜痛、全身のだるさ。特に発症2日目に症状が強くなるとされます。
・精神的苦痛:食べたいのに食べられない。再発への不安、家族への罪悪感、そして「もうよくならないのでは」という絶望感。
・社会的苦痛:食べられなくなることで家庭内の役割を失い、外出や人との交流も減り、経済的な負担も増す。
・スピリチュアルな苦痛:次にいつ誤嚥するか分からない、次は助からないかもしれない、という死への不安。
食べることは生きること――その当たり前が奪われることで、生きる意味が揺らぎます。
こうした全人的苦痛に、私たちは十分に気づけているでしょうか。

生命予後と「サプライズ・クエスチョン」
研究によれば、誤嚥性肺炎で入院した高齢患者の約半数が1年以内に亡くなるとされています。
緩和ケアでよく用いられる「サプライズ・クエスチョン」(この患者さんが1年以内に亡くなったら驚きますか?)を当てはめると、誤嚥性肺炎も十分に緩和ケアの対象となることがわかります。
緩和ケアをどう取り入れるか?
「緩和ケア病棟でなければできない」わけではありません。
むしろ、誤嚥性肺炎は一般病棟や在宅の場面でこそ求められます。
・看護師、リハビリスタッフ、ソーシャルワーカーなど多職種での早期介入
・患者さんだけでなくご家族もケアの対象
・できるだけ早い段階から「症状緩和」「生活の質の維持」を視野に入れる
イギリスでは「すべての患者が緩和ケアの対象」という考え方が浸透しています。
人的資源が整っていることも背景にありますが、まずは「誰もが対象」という認識を持つことが第一歩だと思います。

看護師としての視点
私自身、緩和ケア病棟に勤めていますが、「がん以外は対象外」という現実にジレンマを感じることがあります。
しかし今回の学びから、「緩和ケアは場所ではなく視点」であると改めて感じました。
たとえ誤嚥性肺炎の患者さんが緩和ケア病棟に入れなくても、緩和ケアの視点を持って寄り添うことは、私たち看護師がどの現場でもできることです。

まとめ
・誤嚥性肺炎も緩和ケアの対象である
・患者さんと家族の全人的苦痛に寄り添うことが大切
・緩和ケア病棟でなくても、どの現場でも緩和ケアの視点を持てる
「誤嚥性肺炎の患者さんにも緩和ケアを」
この言葉を胸に、これからの看護を見直していきたいと思います。

今日もゆるーりとね💕