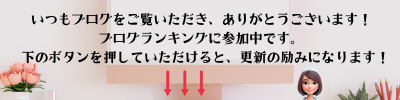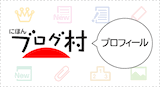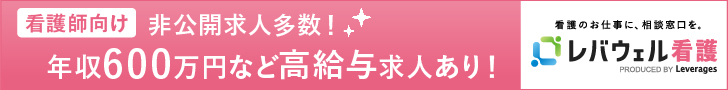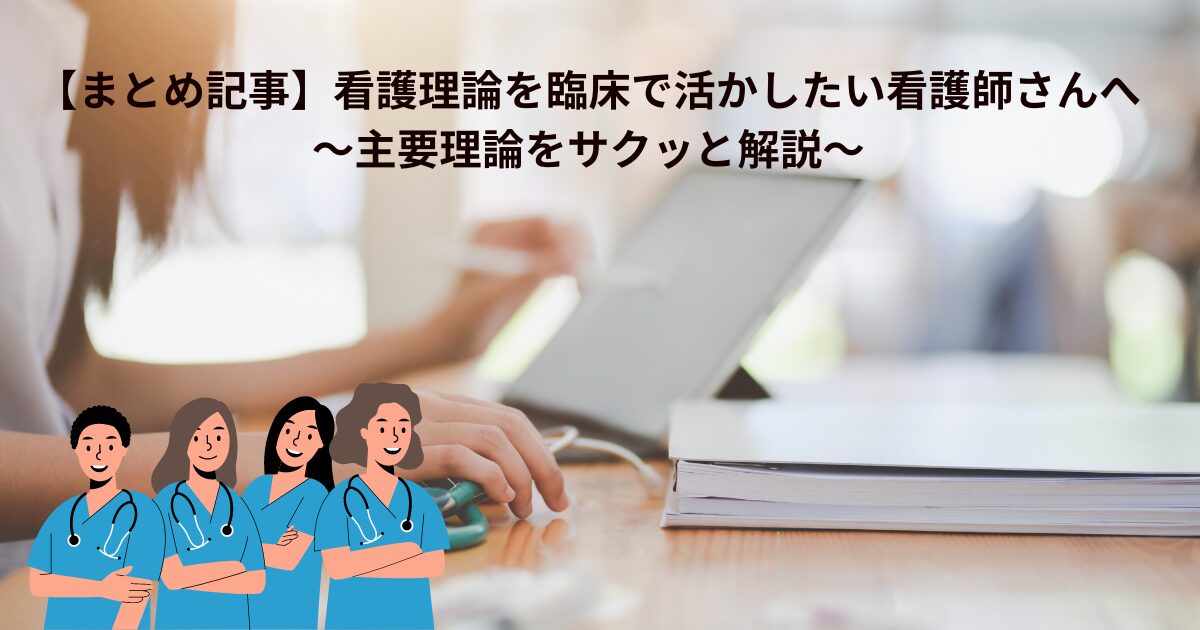こんにちは。このブログの管理者
ゆるーりすと のぴまゆです。
このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。
それではゆるーりとご覧ください。
こんな方におすすめ
- がん看護に携わる医療従事者
- 高齢の親や認知のある家族を持つ人
- 看護倫理やインフォームド・コンセントについて学習中の学生
目次
【「本人には言わないでください」…がん告知に揺れる現場で】
「もう高齢ですし、本人には言わないでほしいんです」
「知らないほうが幸せだと思うんです」
そんな言葉を、がん告知を前にしたご家族から聞くことは、いまだに珍しくありません。
特に緩和ケア病棟では、患者さん自身が“がんであること”を知らずに入院してくるケースも少なくないのが現実です。
でも、ふと立ち止まってしまうのです。
この選択は、本当に“患者さんのため”になっているのだろうか?

【自殺率が3倍に?がん告知が持つリスクと、避けられがちな“真実”】
2024年6月、ダイヤモンド・オンラインに掲載された記事(早稲田大学・村松聡教授)では、
**「がん告知によって自殺率が2~3倍になる」**という調査結果が紹介されていました。
確かに、がん告知を受けた患者はショックを受け、
抑うつ状態に陥ったり、極端な選択をしてしまう危険性もあります。
実際、がん告知をきっかけに自死を選んでしまった例も過去にはありました。
そのため、医師や看護師、家族が告知に慎重になるのは当然とも言えます。
しかし一方で、真実を知らずに周囲の様子から“察してしまう”患者の苦しさもまた、現場では何度も目にしてきました。

【それでも「真実を伝える」べき理由とは】
村松教授は著書『つなわたりの倫理学』の中で、こう問いかけています。
「事実を隠すことは、本当の思いやりか?それとも、思いやりと間違えた“偽り”ではないか?」
そして、例え相手を傷つける結果になったとしても、「人生を左右する重大な事実」は伝えるべきだと述べています。
それは、患者さんの人生の岐路に立つ瞬間。
残された時間をどう過ごすか――
誰に会うか、何を準備するか、自分の人生をどう終えるか。
本人が決めるべき大切な選択肢は、「真実」を知らなければ選びようがないのです。
【告知は“するかしないか”ではなく、“どうするか”の時代へ】
がん告知をめぐっては、法的にも「医師の合理的な裁量の範囲」とされてきましたが、
近年では**“自己決定権”の尊重が重視される時代へと移り変わっています**。
もちろん、心の準備ができていない段階での唐突な告知は、患者を追い詰めるだけです。
重要なのは、伝え方、タイミング、支援体制、そして患者との信頼関係です。
だからこそ、医療者や家族ができることは――
「いまはまだ無理」と思えるときでも、
いつかその人が耳を傾けるタイミングを見逃さず、
その人の“人生の選択”に寄り添える環境を整えることではないでしょうか。

【看護師としての私の思い:人生の主役は、やっぱり本人だから】
患者さんががんと知らずに緩和ケア病棟に入院してきたとき、
私は、そっと心の中で「知っていてほしかったな」とつぶやいてしまうことがあります。
だって、自分の人生の終わりをどう過ごすか、誰よりも選ぶ権利があるのは、本人だから。
確かに、がん告知は慎重に行うべきです。
けれど、「知らない方が楽だから」「もう年だから」といった理由だけで告知が避けられているなら、
それは本人から“選択する力”を奪ってしまっていないでしょうか。
私たち看護師は、告知の“瞬間”だけではなく、
その後の受け止めや、心の整理を支える存在でありたいと思っています。
【まとめ:がん告知は“人生の準備”のためにある】
告知はショックを与えるものかもしれません。
でも、だからといって、伝えないことで患者さんの人生を台無しにしてもよいわけではありません。
誰もが最期まで、自分らしく生きられるために。
がんであることを知ったうえで、「何を大切にしたいのか」を考える時間を持つために。
がん告知は、“終わりを迎える人の人生設計”に必要な、大切な一歩だと私は考えています。
そして願わくば、
がん告知が特別なことではなく、「自然に」「当たり前に」語られる社会になりますように。
その未来に向けて、今日も私は、患者さんと向き合い続けたいと思います。

【あとがき】
がん告知は、今も現場で迷い続けるテーマです。
もしあなたがご家族や大切な人の立場だったら、どう感じますか?
よければ、コメント欄などで皆さんの声もお聞かせくださいね。

今日もyるーりとね💕