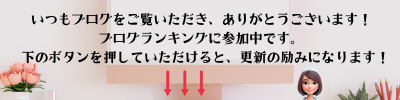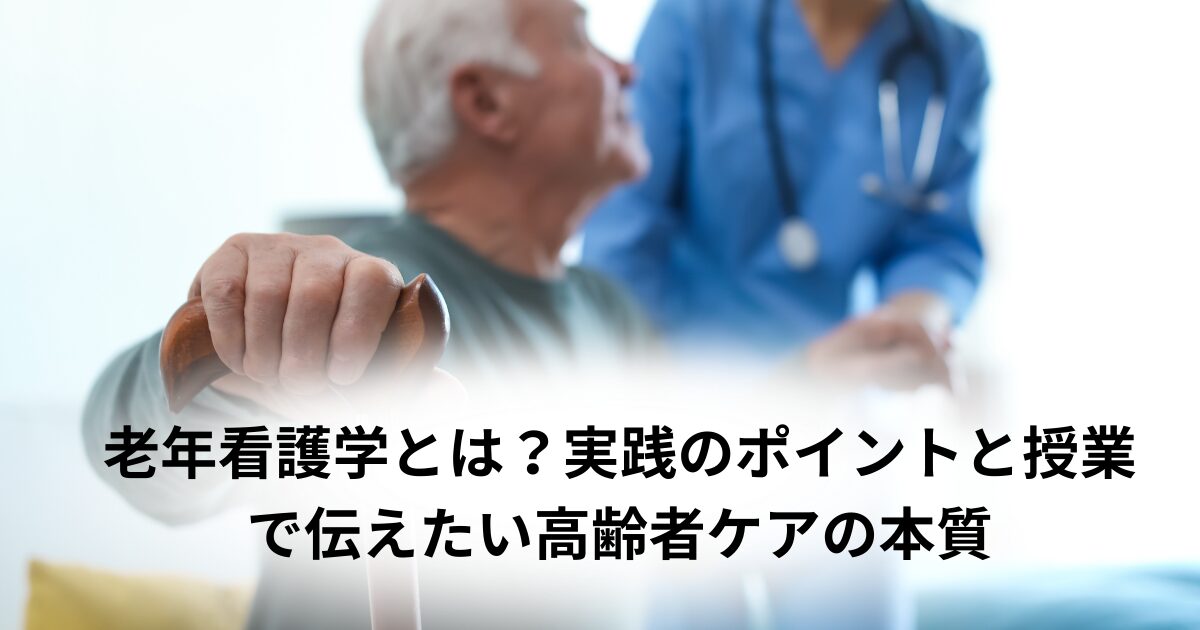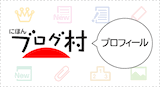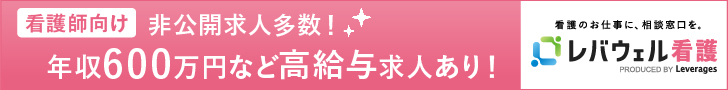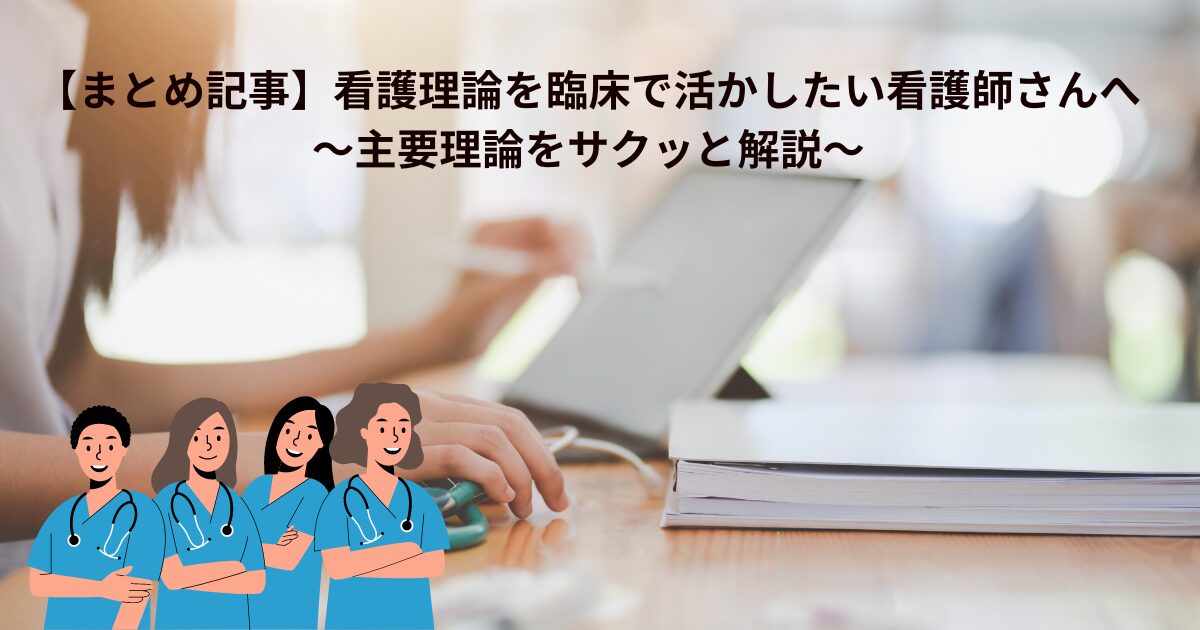こんにちは。このブログの管理者
ゆるーりすと のぴまゆです。
このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。
それではゆるーりとご覧ください。
こんな方におすすめ
- 看護学生さん(特に老年看護学に取り組む方)
- 臨床で高齢者看護に関わる若手看護師さん
- 教育の場で老年期をどう伝えるか悩む看護教員の方
目次
はじめに~老年看護学を担当することになりました
来年度、院外講師として「老年看護学」の授業を担当させていただくことになりました。
これまでは感覚器に関する講義をしていましたが、次年度は「老年期の看護実践」というテーマ。
範囲が一気に広がり、正直なところ悩みました。
ですが、今私が勤務している緩和ケア病棟の患者さんの多くは老年期の方々。
「緩和ケア=老年期の看護」と言っても過言ではありません。
だからこそ、これまでの経験を活かしながら、学生さんに伝えられることがあると考え、お引き受けしました。

老年期とは「老い」だけを意味しない
テキストとして使用するのは、医学書院の『系統看護学講座・老年看護学』です。
そこには「老年期とは多様な変化の時期である」と書かれています。
・身体的変化:感覚器・運動機能の衰え、免疫力の低下
・心理的変化:孤独感、役割の喪失、アイデンティティの揺らぎ
・社会的変化:退職、介護、経済的課題
このように「老い」は単純な身体の変化だけではなく、生き方そのものに関わる多様なテーマを含んでいます。
そして、元気に趣味を楽しむアクティブシニアから、医療や介護が必要な高齢者まで、その姿は本当に幅広いのです。

老年看護学の実践のポイント
老年看護を学ぶうえで、大切にしたいポイントは次のようなものです。
健康寿命を延ばすケア
予防やセルフケア支援を通じて、「元気に生きる時間」をできるだけ長く保つこと。
健康寿命のとらえ方、具体的な支援も考えていきます。
慢性疾患との共生
糖尿病、心不全、認知症など、完治が難しい病と付き合いながら生活を整える支援。
完治が難しいといわれる疾患であっても、日常生活を整えることでむしろ健康に生活することも可能です。
高脂血症、変形性膝関節症の持病がある自分だから伝えられることも。
家族や地域とのつながり
地域包括ケアの中で、家族・多職種・地域と協力しながら支える姿勢。
在宅看護がクローズアップされている今、病院の機能にも変化が表れてきています。
患者である前に生活者であるという視点とその人らしさを支える社会資源も学びます。
エンド・オブ・ライフケア
人生の最終段階をどう生きるか。
ACP(アドバンス・ケア・プランニング)を含め、患者と家族の意思を尊重するケア。
大学で新たに学んだ分野です。
緩和ケアでの実践が活かせる分野といえるでしょう。

緩和ケアと老年期看護の重なり
私が日々向き合っている緩和ケアは、まさに老年期ケアと深く結びついています。
がんや心不全で入院される患者さんのほとんどは高齢者。
「痛みを和らげる」こと以上に大切なのは、 その人らしく生きることを支える 姿勢です。
そのために、学生さんにはACPやエンド・オブ・ライフケアをしっかりと伝えたいと思っています。

教えることで、自分も学ぶ
実は、来年度の老年看護学を担当することは、私自身にとっても学び直しの機会になると感じています。
なぜなら、私ももうすぐ60歳。
学生に「老年期」を語ることは、同時に「これからの自分の生き方」を考えることでもあるのです。

おわりに
老年看護学は、どの看護師も必ず関わる大切な領域です。
学生さんに伝えたいのは、 「老いを支えることは、未来の自分を支えること」 だということ。
来年度の授業を通じて、看護の魅力を共有できるよう準備していきたいと思います。

今日もゆるーりとね💕