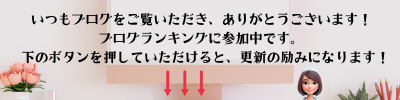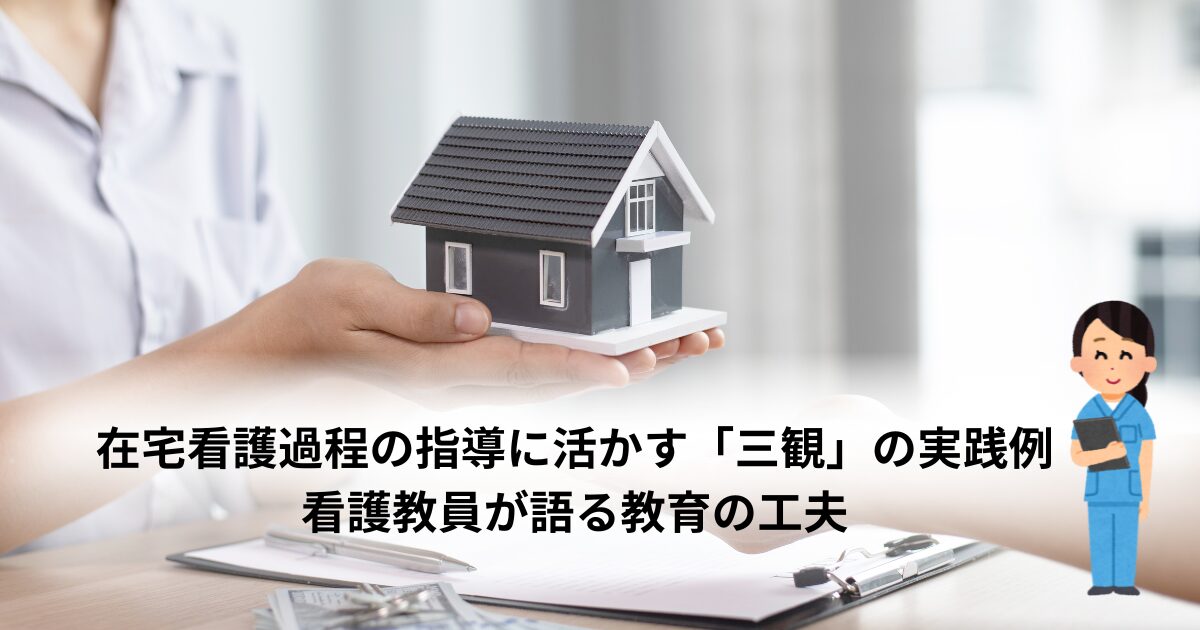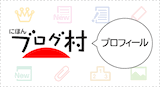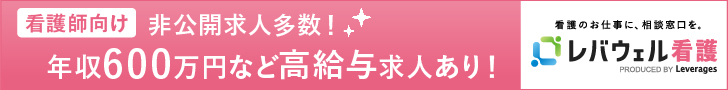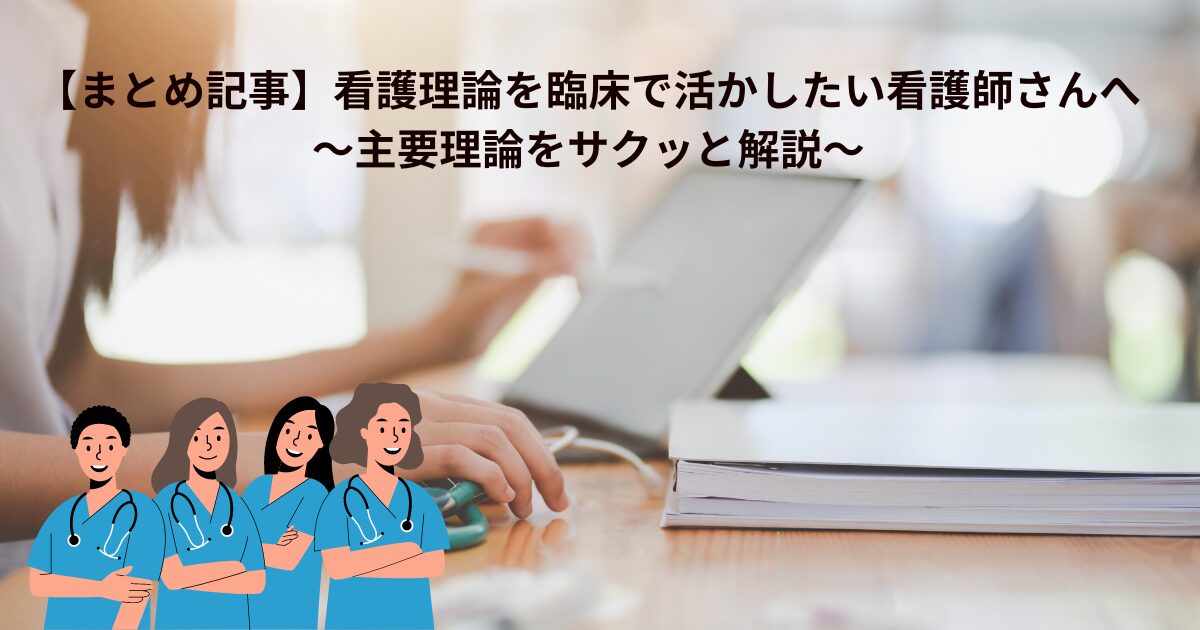こんにちは。このブログの管理者
ゆるーりすと のぴまゆです。
このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。
それではゆるーりとご覧ください。
こんな方におすすめ
- 授業や実習の質を高めたい、学生との関わり方に悩んでいる、授業評価の向上を目指したい方
- 教員養成講習会などに参加している看護師
- 看護師で学生指導を任されるようになった中堅看護師
- 看護学校や大学の教育に関わる人
目次
1. はじめに
看護学生を指導していると、「伝えたいことが伝わらない」「授業がうまく展開できない」と感じることはありませんか?
実はそれ、“三観”が曖昧になっているサインかもしれません。
看護教員・実習指導者として、自身の「学生観・指導観・教材観」を明確に持つことは、授業の質を高め、学生に届く指導へとつながります。
今回は、教育の三観の意味とその活用方法についてご紹介します。

2. 教育の三観とは?それぞれの定義と役割
◆学生観:学生をどう捉えているか
学生観とは、学生をどのような存在として捉えているか、という教員側の見方です。
「学生は未熟だから教える存在」と見るか、「可能性を持ち、自ら学ぶ力のある存在」と見るかで、関わり方は大きく変わります。
成長過程を肯定的に捉える学生観があると、評価や声かけの質も変わります。
時代を捉え、今の学生の価値観や考え方の傾向を掌握することで、どのようなアプローチが有効か考えていくことができます。

◆指導観:どのように教えるか、どう関わるか
指導観は、教育的関わりのスタイルや方針を示す考え方です。
「一方的に教える」「知識を詰め込む」のか、「学生の学びを引き出す」「体験を通して気づきを得る」のか。
指導観がぶれると、授業の軸も定まりません。
実践力を養う看護教育では、主体的な学びを支える指導観が求められます。

◆教材観:教材をどう捉え、活用するか
教材観は、「教材をどう選び、どう扱うか」に関する考え方です。
教材は“教えるための道具”ではなく、“学生の学びを深めるためのきっかけ”という視点が重要です。
例えば症例や実習記録も教材です。
実体験を教材に変える力は、教材観があってこそ育ちます。
実習指導者講習会では、私たちの急性期看護のグループは術後ベッドを教材としました。
術前術後の看護が経験できなくても、術後ベッド作成を学生に体験させることで、そのエビデンスを学ぶことで急性期の看護を学ぶことはできるはずだと考えました。
コロナの時代に、術前術後を学生がリアルタイムに実習できなくても、「動」ではなく「静」でも実習できるよいう、そのような発想を指導者はもつと良いと思います。

私たちは教材としてのベッドを「ケアリングベット」と名付けました。
3. 三観を持つことで変わる授業・実習指導の質
実習指導で、学生が「うまく患者さんと関われません」と悩んだとき。
「学生は試行錯誤しながら学ぶもの」という学生観を持つ指導者なら、寄り添いながら前向きな助言ができます。
一方、「できないのは努力が足りない」と見てしまうと、関わりは否定的なものになりがちです。
授業設計でも、「この教材を通して学生にどんな気づきを促したいのか」「自分の指導は学生の思考を広げているか」など、三観が明確であることで、授業に“意図”が生まれ、指導案も質の高いものになります。

4. 自分の三観を育てるためのヒント
三観は“正解”があるものではありません。
しかし、自分の授業や指導を振り返る中で「私は学生をどう見ているのか」「この教材で何を伝えたかったのか」と問い直すことで、少しずつ明確になっていきます。
同僚と“授業について語る時間”を持つことも、三観を育てる上で非常に有効です。

今回、当時私が教員養成講習会で作成したレポートの事例を紹介します。
興味のある方はこちらをご覧ください。

-

-
在宅看護過程の指導に活かす「三観」の実践例|看護教員が語る教育の工夫
続きを見る
5. まとめ:三観を育てることが看護師育成の質を高める
教育の三観——学生観・指導観・教材観は、教員・指導者にとっての“羅針盤”です。
この3つの視点を明確に持つことが、学生の学びを支え、良質な授業・実習をつくる原動力になります。
「学生の未来を育てる仕事」である私たち教員・指導者自身が、常に三観を問い直しながら成長していくことが、看護教育の質を支える力になるのです。

今日もゆるーりとね💕