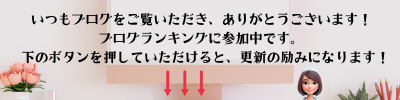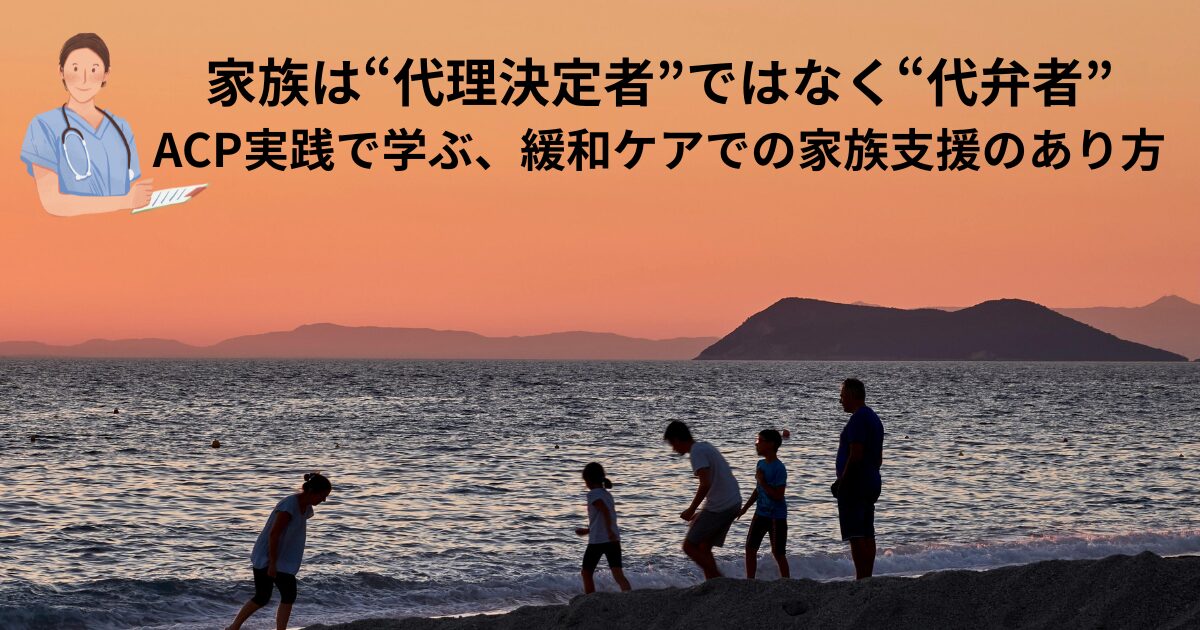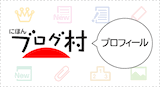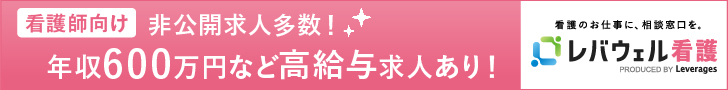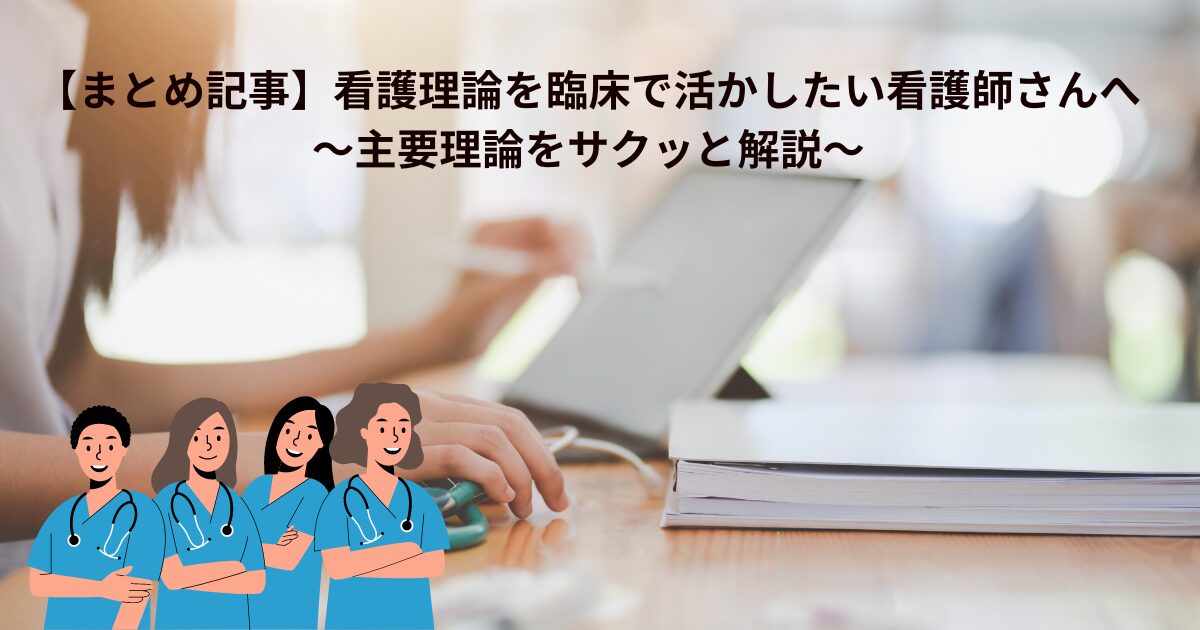こんにちは。このブログの管理者
ゆるーりすと のぴまゆです。
このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。
それではゆるーりとご覧ください。
こんな方におすすめ
- 緩和ケア・在宅医療に関わる医療職(看護師・医師・ケアマネジャーなど)
- ACPの支援を実践したいが「代弁者の選び方」に悩んでいる方
- 家族として患者さんの意思を尊重したい一般読者
目次
🧣はじめに~代弁者という言葉に敏感になる瞬間
先日、日経メディカルAナーシングで「代弁者の決め方」という記事を読み、深く共感しました。
私は先日の緩和ケア医療学会でも、「代理決定者ではなく代弁者である」という視点の重要性を学びました。
-

-
日本緩和ケア医療学会2025 in 徳島【第1弾】ACPと共同意思決定から学ぶ医療者の役割
こんにちは。このブログの管理者 ゆるーりすと のぴまゆです。 このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。 それではゆるーりとご覧ください。 こんな方におすすめ 緩 ...
続きを見る
それ以来、「代弁者」という言葉に敏感に反応するようになり、今回の記事も自然と目に留まりました。

-

-
家族は“代理決定者”ではなく“代弁者”──ACP実践で学ぶ、緩和ケアでの家族支援のあり方
こんにちは。このブログの管理者 ゆるーりすと のぴまゆです。 このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。 それではゆるーりとご覧ください。 こんな方におすすめ 緩 ...
続きを見る
🌿本人の意思を「代わりに」ではなく「代わって伝える」
ACP(アドバンス・ケア・プランニング)の定義には、「本人が意思決定できなくなったときに備え、代わりに意思決定を行う信頼できる人を選ぶプロセス」とあります。
ここでいう“信頼できる人”が、いわゆる代弁者です。
記事に紹介されていたGさんの事例は、とても示唆に富んでいました。
進行したCOPDと認知症を抱えるGさんは「早く家に帰りたい」と繰り返し訴えます。
医療チームはその願いを叶えたいと思う一方で、体力や介護体制を考えるとリスクも大きい。
息子さんは「延命治療を望まない父の意思を尊重したい」と語り、ケアマネジャーは「自宅介護は限界に近い」と指摘する。
――このような複雑な現実の中で、「誰が代弁者になるのか」という問いが浮かび上がります。

✨代弁者を選ぶための3つの問い
記事では、代弁者を選ぶ際に重要な3つの質問が紹介されています。
本人が誰を代弁者にしたいと考えているか
本人がその人に代弁を委ねたいと伝え、その人が了承しているか
本人と代弁者があらかじめ話し合っているか
この3つの確認が、本人の価値観を尊重するACPの根幹を支える鍵になります。
しかし、現実の医療現場ではこのプロセスが十分に踏まれないまま、「家族だから」「長男だから」と自動的にキーパーソンが代弁者と見なされるケースが少なくありません。

🍁看護師としての気づき:本人の「信頼」を確認する姿勢
私自身、緩和ケアの現場で同様の場面を多く見てきました。
「家族が代弁者」という前提で話が進むことは少なくありませんが、実際には本人が最も信頼しているのが、家族以外の人――例えば長年の友人や看護師である場合もあります。
だからこそ、私たち医療者ができるのは「誰が本当に本人の思いを代弁できるか」を、丁寧に確認することだと感じます。
“代弁”とは、本人の声をなりかわって語ることではなく、本人の価値観を引き出し、形にして届ける行為です。
看護師として、患者の人生観や希望を日常の関わりの中で聴き取ることが、ACPの第一歩であり、代弁者を支える根拠になります。

🌈代弁者を「育てる」関わりへ
記事では、豪州のACP教育プログラムで示された代弁者の条件が紹介されていました。
| 項目 | 内容 | 看護現場でのポイント |
|---|---|---|
| ① 本人の価値観・希望をよく理解している | 本人が大切にしている生き方・治療観を知り、過去の発言や行動からその価値観を理解していること。 | 日常会話や生活の中から「その人らしさ」を聴き取る姿勢が重要。 |
| ② 本人の最善の利益を考えて行動できる | 自分の感情や利益ではなく、本人の幸福・尊厳を優先できる。 | 家族の思いと本人の意思が異なる場合、冷静に判断できるかが鍵。 |
| ③ 医療・ケアチームと協働できる | 医療職との対話に参加し、必要な情報を共有しながら意思決定に関われる。 | 医療チームと対立せず、「協働」の意識を持てる関係性が理想。 |
| ④ 感情的・倫理的に安定している | 危機的な状況でも冷静に対応でき、倫理的判断力を持っている。 | 看取りや終末期に直面しても、動揺に流されず本人の意思を尊重できるか。 |
| ⑤ 医療情報を理解し、判断できる | 治療方針やリスク・ベネフィットを理解し、説明を受けて判断できる能力がある。 | 専門用語を理解しきれなくても、医療チームに質問・確認できる姿勢が必要。 |
| ⑥ 本人と信頼関係がある | 長年の関係性や信頼があり、本人が「この人に任せたい」と感じている。 | 「信頼」は最も重要。本人の表情や言葉から確認することも大切。 |
この6項目を読むと、「代弁者になる資格」は肩書きや立場ではなく、その人の生き方や関係性に根ざしていることが分かります。
私たち医療者は、患者さんと家族の間でこの6つの視点を確認しながら、誰が最も「本人の声を代わりに届けられる人」なのかを丁寧に見極める必要があります。
この条件は、突然誰かに備わるものではなく、話し合いと支え合いの中で育まれるものだと思います。
Gさんの息子さんが、葛藤を経て仕事を辞し、父の介護に専念する決断をしたように、
人は“誰かの代弁者”になっていく過程で、少しずつその覚悟と理解を深めていくのかもしれません。

🪶おわりに~誰が「代弁者」なのかを問い直す
私たちはつい、「キーパーソン=代弁者」と決めつけてしまいがちです。
けれど本当に大切なのは、「本人が誰を信頼しているか」「その人が本人の意思を理解しているか」を丁寧に確認すること。
ACPの実践は、答えを急ぐことではなく、“対話の積み重ね”の中にあります。
代弁者とは、本人の声が届かなくなった時に、その人らしさを代わりに伝える人。
そして私たち看護師は、その声が正しく届くよう、そっと支える存在でありたいと思います。

今日もゆるーりとね💕