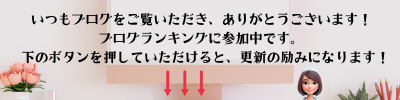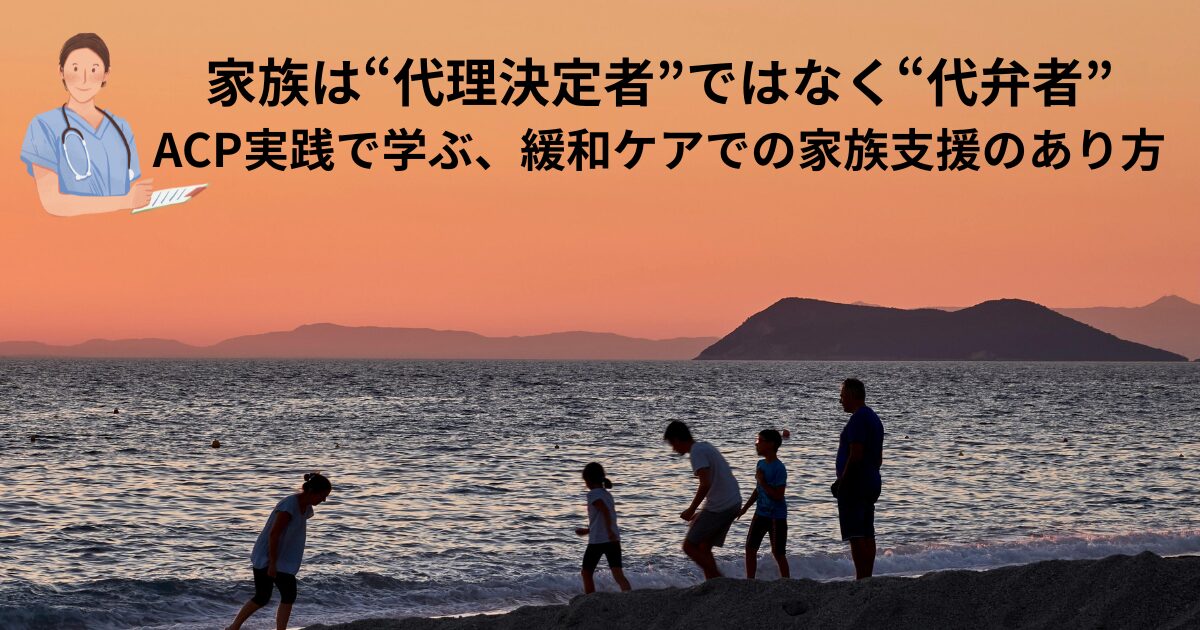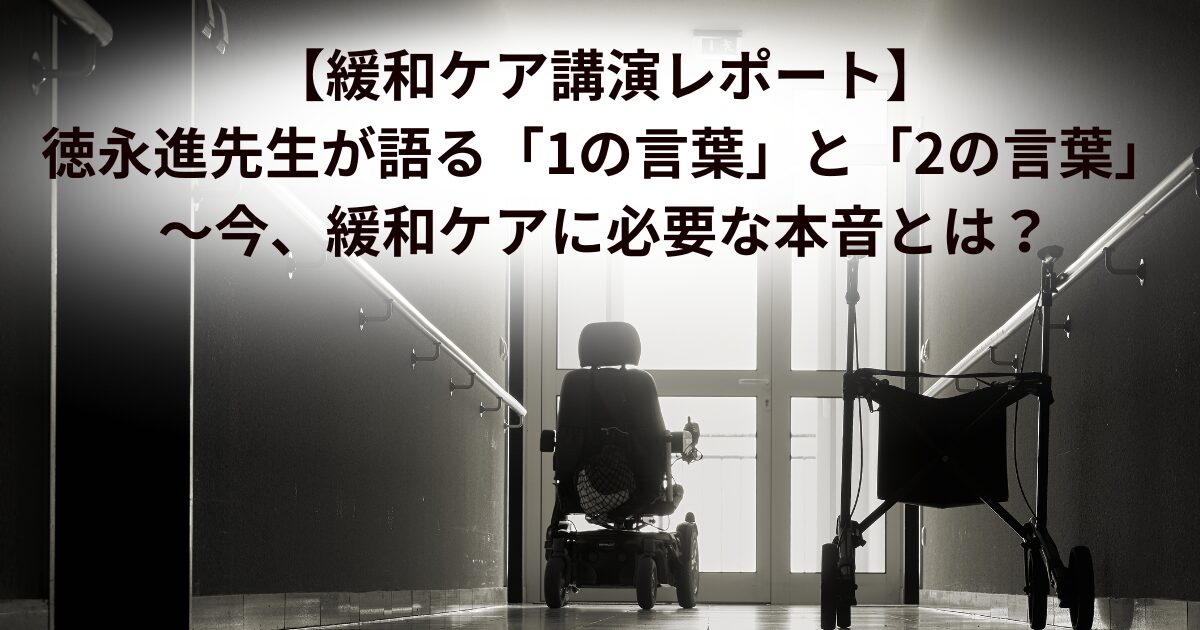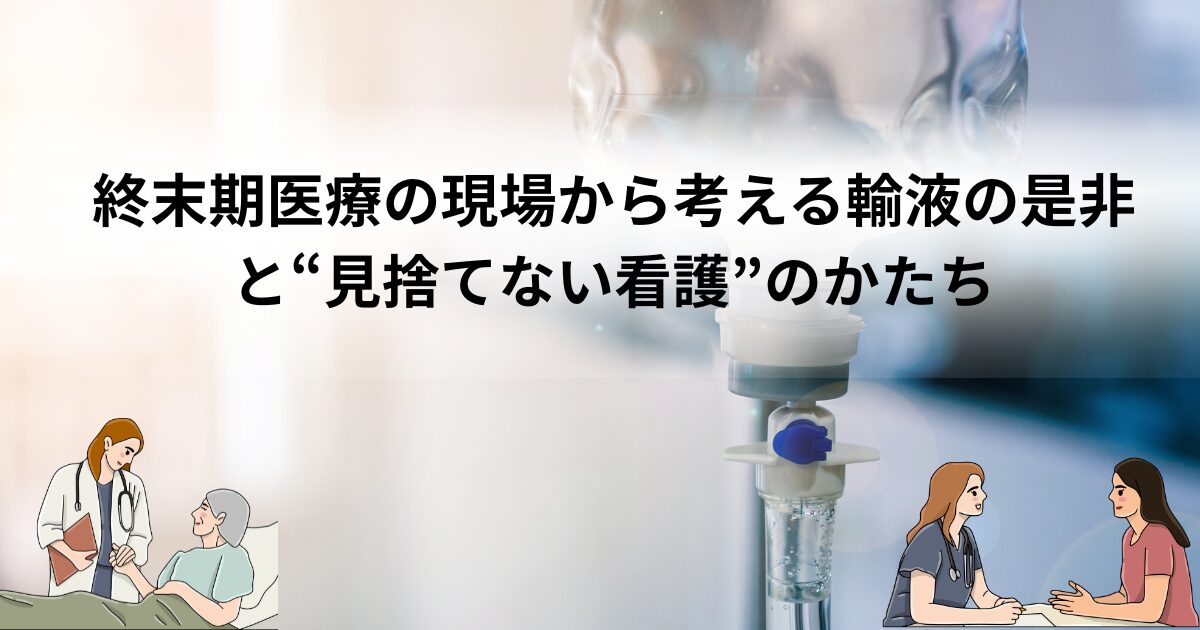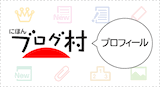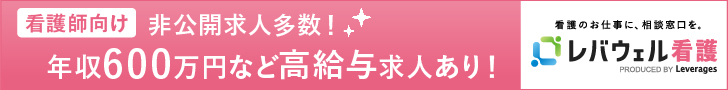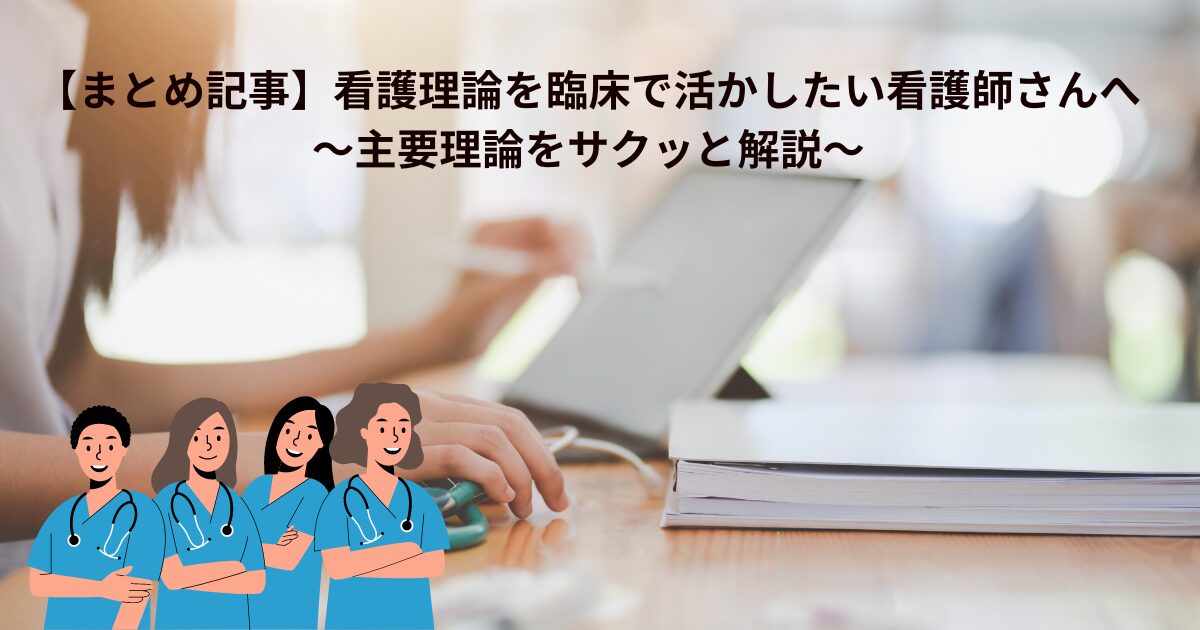こんにちは。このブログの管理者
ゆるーりすと のぴまゆです。
このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。
それではゆるーりとご覧ください。
こんな方におすすめ
- 緩和ケアやACPに関心を持つ看護師・医療従事者
- 家族支援のあり方に悩んでいる看護師
- 医療現場で家族との関わりに迷いを感じている方
- 学生や新人看護師で、ACP実践を学びたい方
目次
【はじめに】
先日、日本緩和ケア学会に参加した際に、印象に残った言葉があります。
それは「家族は代理決定者ではなく、本人の思いを代弁する“代弁者”である」という言葉です。
-

-
日本緩和ケア医療学会2025 in 徳島【第1弾】ACPと共同意思決定から学ぶ医療者の役割
こんにちは。このブログの管理者 ゆるーりすと のぴまゆです。 このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。 それではゆるーりとご覧ください。 こんな方におすすめ 緩 ...
続きを見る
この言葉を聞いたとき、私はあらためて家族への関わり方に注意しなければならないと感じました。
日々の緩和ケアの現場で、家族が「本人に代わって決めなければならない」苦悩を抱える姿を何度も目にしてきたからです。
そんな中、日経メディカルで掲載された「代弁者と医療選択について話し合う」という記事に、まさに現場で活かせる具体的なアプローチが紹介されていました。
今回はその内容を共有しながら、私自身の緩和ケアの実践にどう結びつくかを考えてみたいと思います。

■ 代弁者との対話の基本 ―「本人が望むであろう選択」を探る
記事では、「対話の中から本人が好むであろう選択を推定し、治療やケアに反映させる」ことが大原則とされています。
たとえ本人が意思表示できない状態であっても、過去の言葉・生活・価値観から“本人らしい選択”を一緒に見出していく姿勢が大切です。
たとえば、「本人はどんなことを大切にしていたか」「どんな生活を望んでいたか」など、代弁者に“経験としての記憶”を尋ねることで、圧の少ない自然なコミュニケーションが生まれるといいます。
このとき、「どんなお話をされたことがありますか?」と問いかけることで、代弁者は本人の思いを語りやすくなります。
私自身も臨床の中で、質問のトーン一つで家族の語りが変わることを何度も感じています。

-

-
【緩和ケア講演レポート】「徳永進先生が語る「1の言葉」と「2の言葉」~今、緩和ケアに必要な本音とは?
こんにちは。このブログの管理者 ゆるーりすと のぴまゆです。 このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。 それではゆるーりとご覧ください。 こんな方におすすめ 緩 ...
続きを見る
■ 家族の「理解・不安・希望」を丁寧に聞き取る
家族の理解を確認することは、ACPの第一歩です。
病状をどう受け止めているか、どのような不安や疑問を抱えているかを尋ねることで、家族の感情や思考の整理を促します。
たとえば、胃ろうの選択を迫られた家族に対して、医療者が「経口摂取を続けた場合のリスク」や「経鼻胃管のメリット・デメリット」を具体的に説明し、“保留も選択肢”として提示することも重要です。
結論を急がず、「考える時間」を共有する姿勢が、結果的に家族の納得感につながります。

■ 「本人の希望」だけでなく「家族の感情」も尊重する
ACPの目的はあくまで「本人の意思の尊重」ですが、家族の感情に寄り添うことも同じくらい大切です。
記事でも「代弁者に過度なストレスが生じないように配慮すること」と述べられています。
家族は“理”と“情”の間で揺れ動きます。
「頭では分かっているけれど、心がついていかない」──その葛藤を理解し、まず受け止める姿勢が、信頼関係の礎となります。
私の経験でも、「どうしても食べさせたい」という家族の思いに、医学的な説明だけでは届かない場面がありました。
そんなとき、「それほどまでに思われる理由」を聴き取ることで、家族が少しずつ“自分の中の整理”をつけられるようになることがあります。

-

-
終末期医療の現場から考える輸液の是非と“見捨てない看護”のかたち
こんにちは。このブログの管理者 ゆるーりすと のぴまゆです。 このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。 それではゆるーりとご覧ください。 こんな方におすすめ 終 ...
続きを見る
■ 後悔のないACPは存在しない ―「人権活動」としてのACP
記事の最後には、「ACPは人権活動であり、後悔がつきもの」と書かれていました。
この言葉はとても印象的でした。
どんなに誠実に話し合い、最善を尽くしても、「あのときこうしていれば…」という思いは誰しも抱くものです。
ACPには“正解”はなく、“納得の過程”こそが大切なのだと改めて感じます。
緩和ケアに携わる私たち看護師は、その“納得の過程”を支える立場です。
家族が「理解者」として医療者を感じられるよう、これからも対話の姿勢を大切にしていきたいと思います。

【まとめ】
家族は代理決定者ではなく、本人の思いを伝える「代弁者」。
この視点を持つことで、ACPの実践はぐっと現実的で温かいものになります。
「本人の希望を尊重し、家族の気持ちにも寄り添う」
──それは、理屈や正解を超えて、人と人としての信頼を紡ぐプロセスです。
これからも一人ひとりの“物語”に耳を傾けながら、ACPを広めていきたいと思います。

今日もゆるーりとね💕