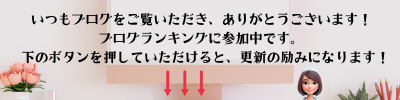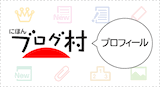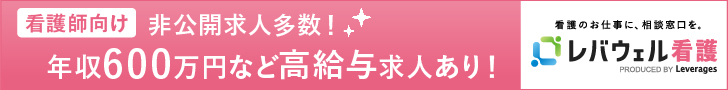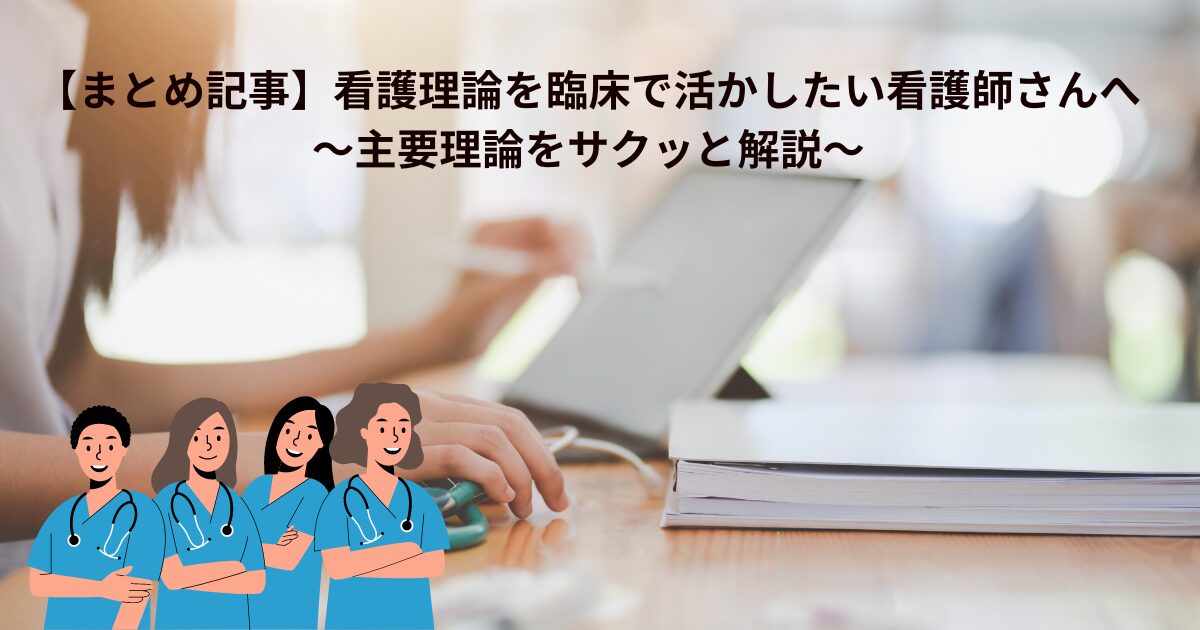こんにちは。このブログの管理者
ゆるーりすと のぴまゆです。
このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。
それではゆるーりとご覧ください。
こんな方におすすめ
- 自分のボーナスの仕組みに疑問を感じた看護師
- 評価制度にモヤモヤを感じている医療従事者
- 国公立→民間病院へ転職したばかりで仕組みに戸惑っている方
- 看護師のキャリアアップや目標管理に興味がある方
目次
はじめに~今年のボーナス、どうでしたか?
今年の夏のボーナス、あなたの手元にはどう届きましたか?
「思ったより多かった!」「減ってしまった…」「今年は支給なしだった…」

看護師であっても、ボーナスの支給は年々厳しさが増している印象がありますよね。
私が働く病院でも、先日、人事考課に関する研修があり、ボーナス支給の仕組みや評価制度についての話がありました。
正直なところ、その内容を聞いてはじめて、「ああ、ボーナスってこういう風に決まってたのか…!」と腑に落ちた部分も多くありました。
今回は、その学びをシェアしながら、あなたがもらっているボーナスの「正体」について、わかりやすく解説していきたいと思います。
ボーナスとは?目的と意義
まず、ボーナス(賞与)とは何か。
ボーナスは、基本的に「従業員の労働に対する報奨金」として、年に1〜2回支給されるものです。
業績への貢献や日頃の働きへの評価を金額として表すものですが、実はボーナスにはいくつかの種類があり、その仕組みや考え方は会社や病院によって異なります。

ボーナスの3つの種類:あなたの職場はどのタイプ?
賞与は大きく分けて以下の3種類に分類できます。
① 基本給連動型賞与(固定賞与)
・公務員や一部の企業で採用
・毎月の基本給に連動して支給される
・人事評価や業績に関係なく、一定の算定基準で計算
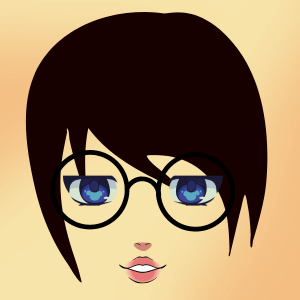
② 決算賞与
・企業の年度決算の業績によって支給が決定
・業績が良ければ支給あり、悪ければ「ゼロ」の可能性も
・明確な基準があるわけではなく、会社の裁量も大きい
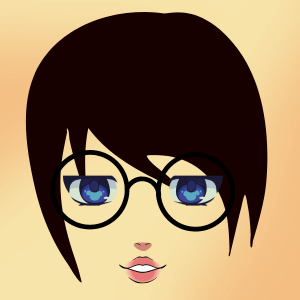
③ 業績賞与(評価連動型賞与)
・評価制度と業績に基づく支給
・個人の人事評価(目標管理・役割行動評価など)をもとに、全体の賞与総額から按分
・民間病院で多く導入されている
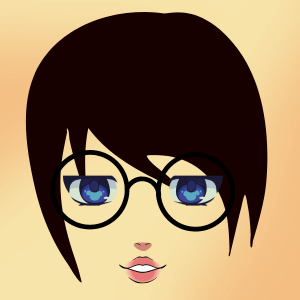

私の病院のしくみ:評価と分配
研修で学んだ内容をシェアすると、業績賞与型の場合、まずは病院全体の業績に基づいて「賞与原資」が決まります。
その後、各職員の評価に応じて「誰に、どれくらい支払うか」が決まるのです。
私たち看護師は、年度のはじめに目標管理シートを提出し、それに基づいた評価と、日常の役割行動に対する評価を受けます。
評価はA〜Eの5段階評価で行われ、それに応じて支給額が変動します。

評価の落とし穴「頑張ったのに評価が低い…」が起きる理由
ここで、多くの人が抱く疑問が生まれます。
「私、頑張ったのに評価が低かった…どうして?」
その理由のひとつに、「評価分布割合基準」という仕組みがあります。
これは、全体のバランスを取るために、A評価が多すぎる部署、特定部門に偏りが出ないように人数配分を調整するためのものです。
つまり、同じくらい頑張っても「部署の中での相対評価」によって、BやCになる場合もあるのです。

国立出身者として感じた違和感
私は以前、国立病院に勤めていたこともあり、「業績をみんなで分け合う」という発想には、最初かなり戸惑いがありました。
でも、これは民間病院ではごく普通の考え方。

病院という組織であっても、「組織全体の経営を支える一員」という意識を持つことが求められているのだと、少しずつ理解するようになりました。
ボーナスを知ることは、自分を守ること
今回の研修を通して、改めて感じたことは、
「仕組みを知ることが、自分を守ることにつながる」ということです。
評価やボーナスに不満があるとき、「なんで私だけ…」と感じてしまいがちですが、その背後にはこうした制度や分配のルールがあります。

納得できないこともあるかもしれません。
でも、まずは知ること。
そして、自分の行動をどう評価につなげるかを考えることが、未来の自分の待遇を守る力になるのではないでしょうか。
まとめ~評価は未来の自分への投資
このブログを書いたのは、ボーナスに一喜一憂するのではなく、仕組みを理解し、次に向けて前向きな行動につなげてほしいという思いからです。
賞与は、がんばった証でもありますが、必ずしも“感情”と一致するものではないというのが現実です。
でも、評価を受ける側として、自分の立ち位置を知り、納得し、次の一歩に生かすこと。
それが、看護師としての成長にもつながると感じています。

今日もゆるーりとね💕