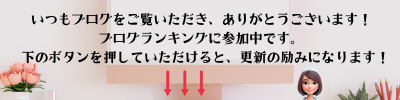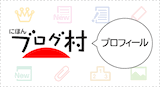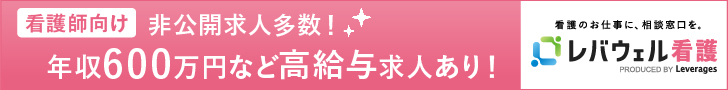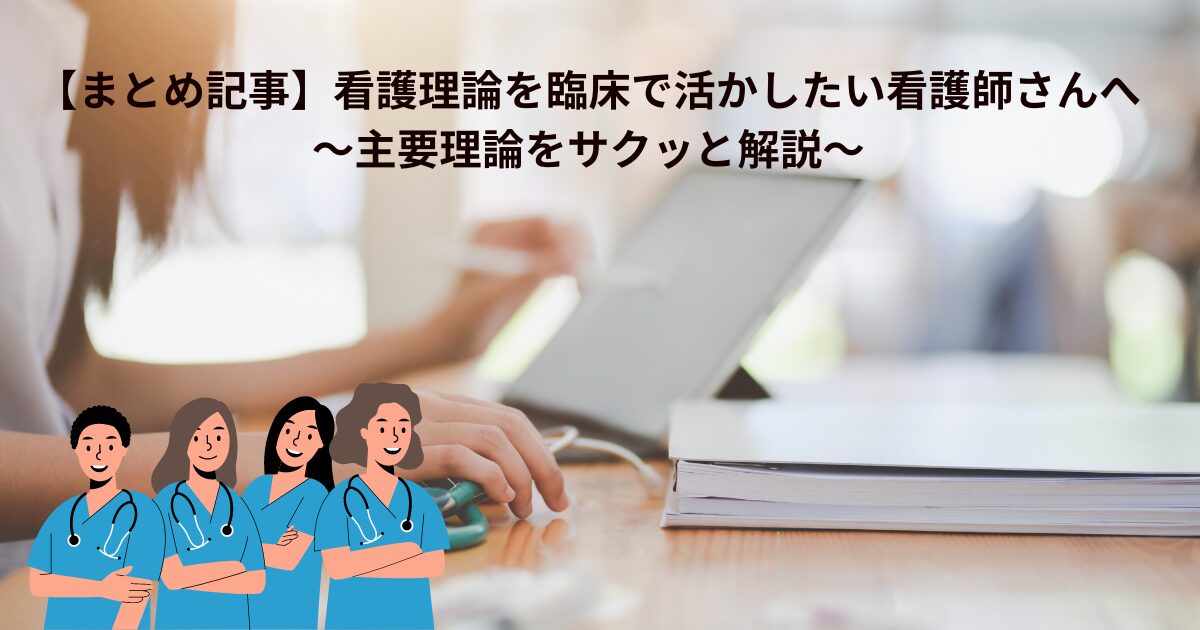こんにちは。このブログの管理者
ゆるーりすと のぴまゆです。
このブログはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を利用しています。
それではゆるーりとご覧ください。
こんな方におすすめ
- 終末期の家族を介護している方
- 緩和ケアに関心のある一般市民の方
- 看護師や介護職など、患者や家族の心に寄り添いたい医療従事者
目次
①はじめに~当たり前の日常にある「食べる」という行為
「食べる」ことは、私たちの生活の中でもっとも自然で、当たり前の行動のひとつです。
おいしいものを食べて幸せを感じ、体を作り、エネルギーを得る。
健康なときには、それがどれほど尊いことか、あまり意識することはありません。
しかし、病を得て、特に終末期を迎えたとき、「食べる」という行為はまったく違う意味を持ち始めます。
先日参加した市民向けの緩和ケアイベントでは、「食」をテーマに、そんな“食べる”という日常の行為を改めて考える時間となりました。

②病気によって変化する「食」の意味
がんをはじめとする重い病を患うと、からだの中ではさまざまな変化が起こります。
栄養を摂ることが、かえって病の進行を助けてしまうこともあります。
「がん悪液質」と呼ばれる状態では、筋肉量が減り、体重が落ち、どんなに食べようとしても食欲がわかず、体が受けつけなくなってしまうのです。
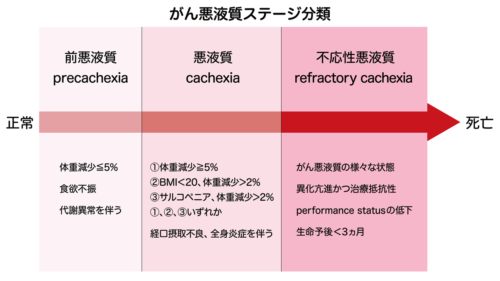
そんなとき、多くの家族はこう言います。
「食べないと元気になれないよ」
「少しでも食べて」
けれど、当の患者さんは、食べることそのものが苦痛になっている場合もあります。
食事のにおいで吐き気を催すこともあり、「食べなきゃ」という周囲の期待がかえってつらく感じられることもあるのです。
③食べられなくなったとき、家族の想い
「もう食べられない」と聞くと、多くの家族は「もう終わりなのでは」と感じてしまいます。
「まだ食べてほしい」「あきらめたくない」という気持ちは、愛情の表れです。
でも、本当に“食べないこと”は“あきらめること”なのでしょうか。
患者さんの中には、もう栄養としての食ではなく、「氷を口に含む心地よさ」「少しの水分のうるおい」「家族と過ごす食卓のぬくもり」に価値を見出している方もいます。
食べることを手放すことは、人生を手放すことではありません。
それは、“生きる形を変える”という、静かな選択なのかもしれません。

④“食べる”を超えた「食」の支援へ
緩和ケアにおける「食」の援助とは、栄養を摂らせることだけではありません。
「食べる=栄養」という固定観念を一度手放し、「食べる=楽しむ」「食べる=つながる」といった新しい意味を見出すことができます。
たとえば、
一口でも好きなものを味わう
家族と一緒にテーブルを囲む
食べられなくても「香り」を楽しむ
そうした小さな時間にこそ、その人らしい“生”が宿ります。
看護師として、家族として、私たちは「食べることを支える」から「食べる時間を共に感じる」支援へと、意識をシフトしていくことが大切だと感じました。

⑤まとめ~手放すことは、あきらめではない
「食べる」という行為は、単なる栄養摂取ではなく、人と人をつなぐ“心の営み”です。
食べられなくなっても、そこには“想い”があり、“ぬくもり”があります。

食べることを手放す勇気。
それは、患者さんの生き方を尊重し、家族がそっと寄り添う、最期までの愛の形なのかもしれません。

今日もゆるーりとね💕